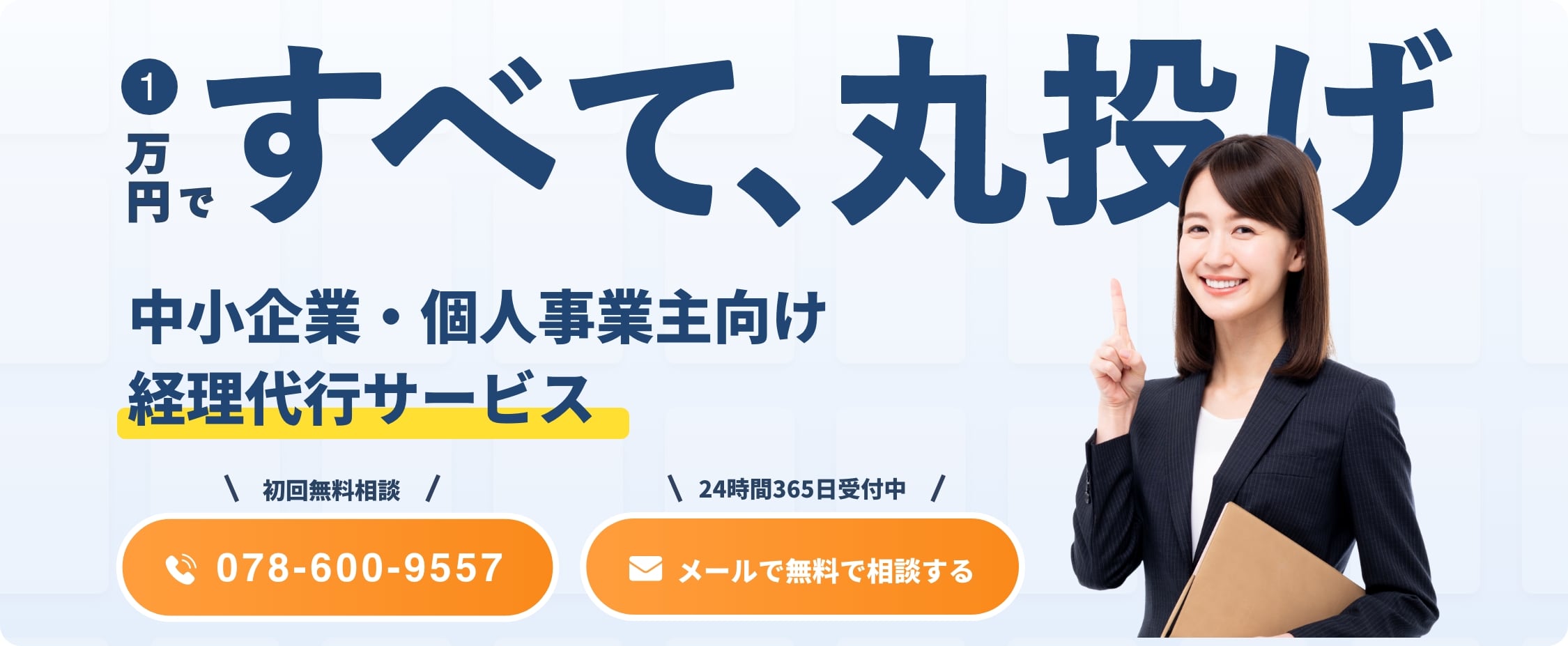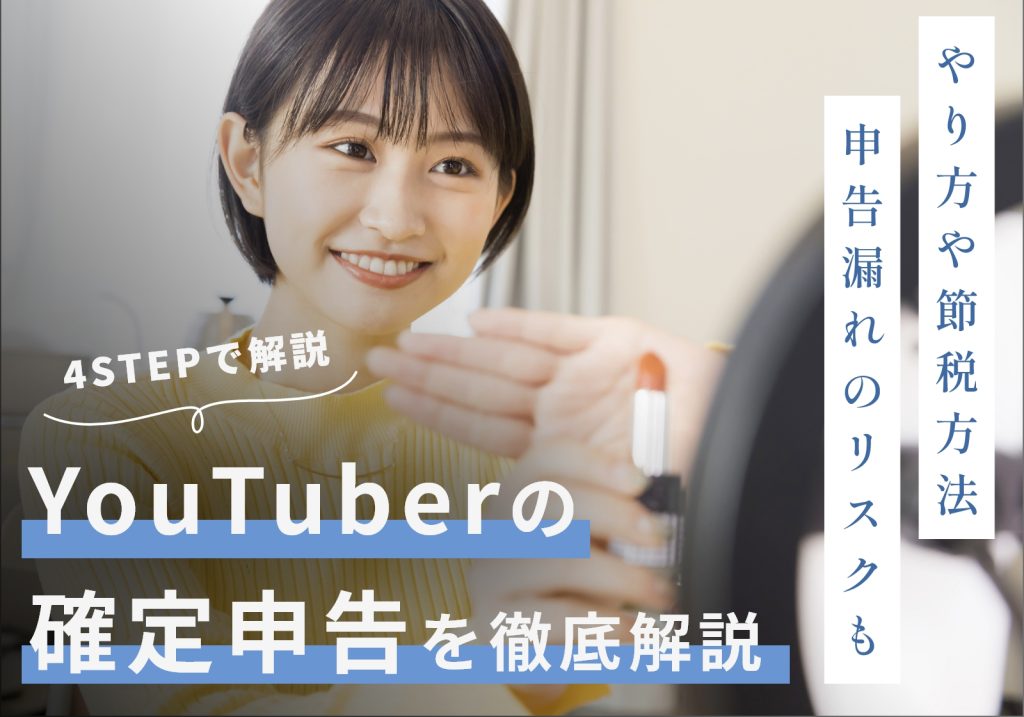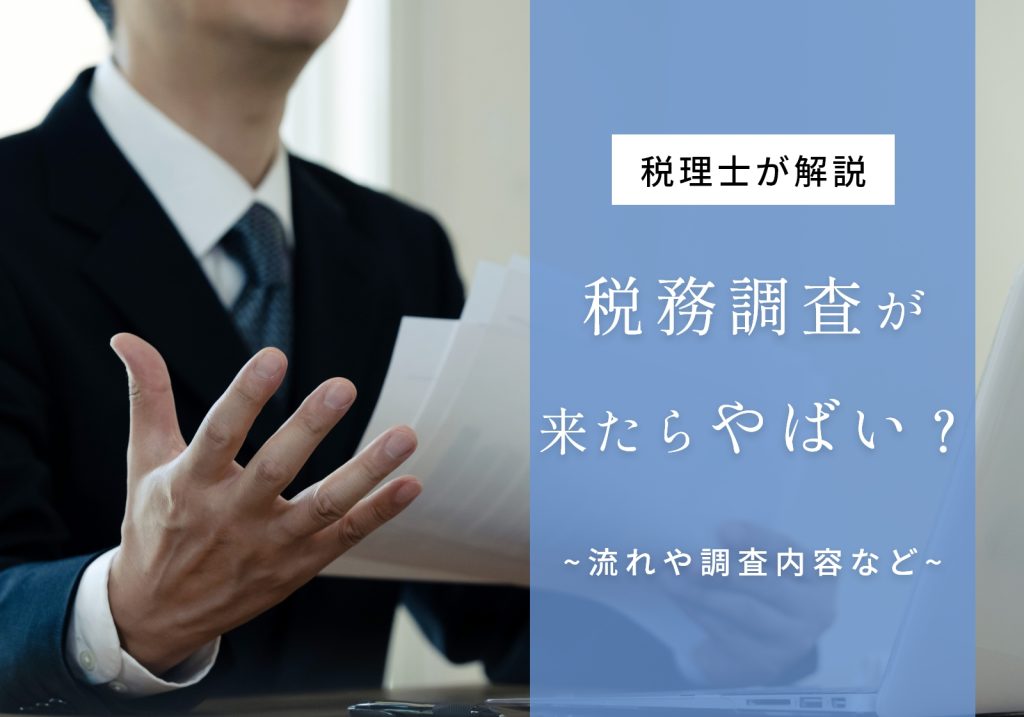
税務調査の対象になった時点で「やばい」可能性が高いです。対応を誤ると、人生が変わってしまう結果を招きかねません。
取られる額は人それぞれです。数千万円の追徴課税を課されるケースもあります。
「税務調査の対象になって焦っている」「正しく申告できたか不安で、税務調査について知りたい」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
今回は税務調査が入るとやばい理由や、いくら取られるのか、最悪の結果を防ぐためにやるべき3つのことなどについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、「税務調査がいかにやばいのか」を理解できます。
目次
【結論】税務調査が入るとやばい
税務調査の連絡が来た際、「少しのミスはあるかもしれないが、大したことはないはずだ」と楽観的に考えてしまうかもしれません。
しかし、税務調査の対象になった時点で、それはすでに「やばい」状況です。なぜなら、税務署は原則として無作為に調査先を選んでいるわけではないからです。
税務署は、限られた人員と時間の中で調査を行います。
そのため「申告内容に誤りや漏れがある可能性が高い」と判断された事業者だけを、調査対象としてリストアップします。
わざわざ「空振り」に終わる可能性が高い事業者を調査するほど、暇ではありません。
税務調査の対象になると、約8割の確率で何らかの指摘を受け、追徴課税を課されます。
税務調査ではいくら取られる?
税務調査でいくら取られるのかは、人それぞれ異なります。
申告漏れの金額や悪質性によって、数十万円で済む場合もあれば、数千万円に膨れ上がるケースもあるでしょう。
追徴課税の税率は、以下のとおりです。
| 種類 | 税額 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 15〜30% |
| 過少申告加算税 | 10〜15% |
| 不納付加算税 | 10% |
| 重加算税 | 35〜40% 隠蔽を繰り返した場合は+10% |
| 延滞税 | 未納額×利率×日数÷365 ※利率は2.4%か8.7% |
「延滞税+加算税のいずれか」の形で追徴課税を課されるのが一般的です。
追徴課税の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:税務調査の追徴課税とは?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説
税務調査ではどこまで調べられる?
税務調査では必要に応じて、以下のようにあらゆる書類を調べられる可能性があります。
- 会計帳簿
- 領収書
- 請求書
- 契約書
- 預金通帳
なお、調べられる書類については、事前通知の際に伝えられます。
税務調査では、過去3年分を調べるのが一般的です。悪質性が認められる場合は、5年分や7年分に伸びます。
また、反面調査が行われるケースもあります。反面調査とは、納税者本人ではなく、取引先や関係者に対して行われる調査のことです。
反面調査が行われると、取引先に迷惑をかけたり、信用を大きく損なったりしてしまいます。
関連記事:税務調査は何年分調べられる?の答えは3年分!5年・7年になるケースや今からできる準備について解説
税務調査で最悪の結果を招かないないためにやるべきこと
税務調査への対応を誤ると最悪の結果を招いてしまうかもしれません。こうした”やばい”状況を防ぐためにやるべきことは、以下の3つです。
- 嘘の証言や資料の偽造・隠蔽をしない
- 税理士への迅速な相談
- 日頃の丁寧な確定申告
それぞれ詳しく解説します。
嘘の証言や資料の偽造・隠蔽をしない
税務調査において、最もやってはいけないのが嘘をつくこと、そして証拠資料を偽造・隠蔽することです。
調査官は税金のプロなので、嘘は簡単に見抜かれます。そして嘘がバレると、調査期間が伸びるなど、より厳しく調査が行われます。
単なる計算ミスや解釈の違いといった「申告漏れ」ではなく、意図的な所得隠しである「脱税」と認定され、重加算税を課される可能性も高くなるでしょう。
金額によっては、逮捕・起訴に至る可能性すらあります。
不利な事実があったとしても、正直に認め、誠実に対応しましょう。これが、ダメージを最小限に抑える唯一の道です。
税理士への迅速な相談
税務調査の連絡が来たら、できるだけ早く、可能であればその日のうちに税理士に相談をしましょう。
税務調査は、税法のプロである調査官と、法律の解釈や事実認定を巡って対等に渡り合う「交渉」の場です。
専門知識のない状態で立ち向かっても、不利な内容を受け入れさせられてしまうのが関の山です。
税理士は、税務調査当日に立ち会います。不当な指摘や法律の拡大解釈に対しては、税理士が法的根拠に基づいて毅然と反論し、あなたの正当な権利を守ります。
税務調査には、準備が欠かせません。できるだけ早く相談することで、税理士が万全の準備をして当日に臨めます。
関連記事:税理士に税務調査を依頼する際に知っておくべきことを1から10まで解説
日頃の丁寧な確定申告
税務調査の対象になると、約8割の確率で何らかの指摘を受け、追徴課税を課されるとお伝えしました。
つまり、そもそも税務調査の対象にならないことが大切です。
そして税務調査の対象にならないためには、日々の丁寧な確定申告が欠かせません。
例えば個人事業主が税務調査の対象になる確率は、0.5%とされています。なかには、生涯一度も税務調査の対象にならない方もいます。
正しく確定申告を行いたいのであれば、税理士への依頼がおすすめです。
税務調査のリスクを減らせるだけでなく、最大限の節税ができたり、確定申告の面倒な手間から解放されたりといったメリットもあります。
関連記事:確定申告を税理士に丸投げしたい個人事業主必見!費用や損に繋がるデメリットを紹介
税務調査が入るとどうなる?流れを解説
税務調査の大まかな流れは、以下のとおりです。
- 事前通知が来る
- 日程を決める
- 当日に向けた準備をする
- 税務調査当日
- 修正申告
1つずつ詳しく見てみましょう。
事前通知が来る
調査を実施したいと考えている日の1〜2週間前に、担当調査官から電話による連絡が入ります。
この電話で、調査の目的や対象期間などを伝えられます。
突然の連絡に動揺するかもしれませんが、その場で即答する必要はありません。
できれば、「スケジュールを確認して折り返します」「税理士と相談します」と伝え、一度電話を切りましょう。
そうすることで、冷静かつ万全の態勢で対応ができます。
関連記事:税務調査の事前通知が来た人必見!その後の流れや税理士に依頼すべき理由を解説
関連記事:税務署からの電話の理由は税務調査?用件や取るべき行動を紹介
日程を決める
税務署から提示された調査日時を、そのまま受け入れる必要はありません。
顧問税理士のスケジュールが合わない、あるいは帳簿の準備に時間が必要といった正当な理由がある場合は、日程の変更を申し出ましょう。
日程交渉は、万全の準備態勢を整えて調査を有利に進めるための、最初の「交渉」の場です。
当日に向けた準備をする
調査の日程が確定してから当日までの行動が、調査の結果を最も大きく左右すると言っても過言ではありません。
まず、調査対象となる期間(通常3年分)の会計帳簿と、その裏付けとなる領収書や契約書といった証拠書類を、すぐに提示できるように整理します。
そして調査官に指摘されそうな箇所を洗い出し、受け答えのシミュレーションを実施します。
税務調査当日
税務調査は、事業の概要に関するヒアリングから始まり、その後、帳簿と証拠書類を照合する本格的な調査へと移ります。
この際の対応の鉄則は、「聞かれたことにだけ、事実に基づいて簡潔に答える」ことです。
良かれと思って話した余計な一言が、かえって新たな疑問を生み、調査期間が長引いてしまうケースは少なくありません。
修正申告
実地調査が終了しても、すぐに結論が出るわけではありません。調査官は持ち帰った資料などを精査し、後日、指摘事項をまとめて納税者に伝えます。
その内容について双方の合意が得られた場合、「修正申告」を行います。
修正申告書を提出し、不足していた本税に加えて、ペナルティである加算税や延滞税を納付することで、税務調査は終了です。
関連記事:税務調査後に修正申告をする流れ!しないとどうなるか、加算税・延滞税の種類などを解説
税務調査の対応は永安栄棟税理士事務所にお任せください
永安栄棟税理士事務所では、税務調査完全サポートパックを提供しています。プランの詳細は以下の通りです。
- 事前打ち合わせ・資料確認
- 調査の立ち会い
- 税務署との調整
- 修正申告書の提出
料金は30万円〜となっており、要望に応じて最適なプランを提案させていただきます。
永安栄棟税理士事務所では、税務調査歴40年超の元特別国税調査官をはじめとしたスタッフが、豊富な経験をもとにサポートいたします。
これまでサポートを行ったほぼすべてのお客様で、税務調査サポート費用を上回る追徴課税の減少を実現しました。

弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。プラン詳細については、以下をチェックしてみてください。
まとめ
税務調査が入るとやばい理由やいくら取られるのか、また最悪の結果を招かないためにやるべき3つのことなどについて解説しました。
税務調査の対象になってしまった場合は、できるだけ早く税理士に相談しましょう。また、嘘や隠蔽は絶対にやめてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「税務調査完全サポートパック」を詳しく見てみる
そして、そもそも税務調査の対象にならないように、正しく確定申告を行うことが大切です。
永安栄棟税理士事務所でも「確定申告丸投げパック」を提供しています。詳しくは以下をチェックしてみてください。