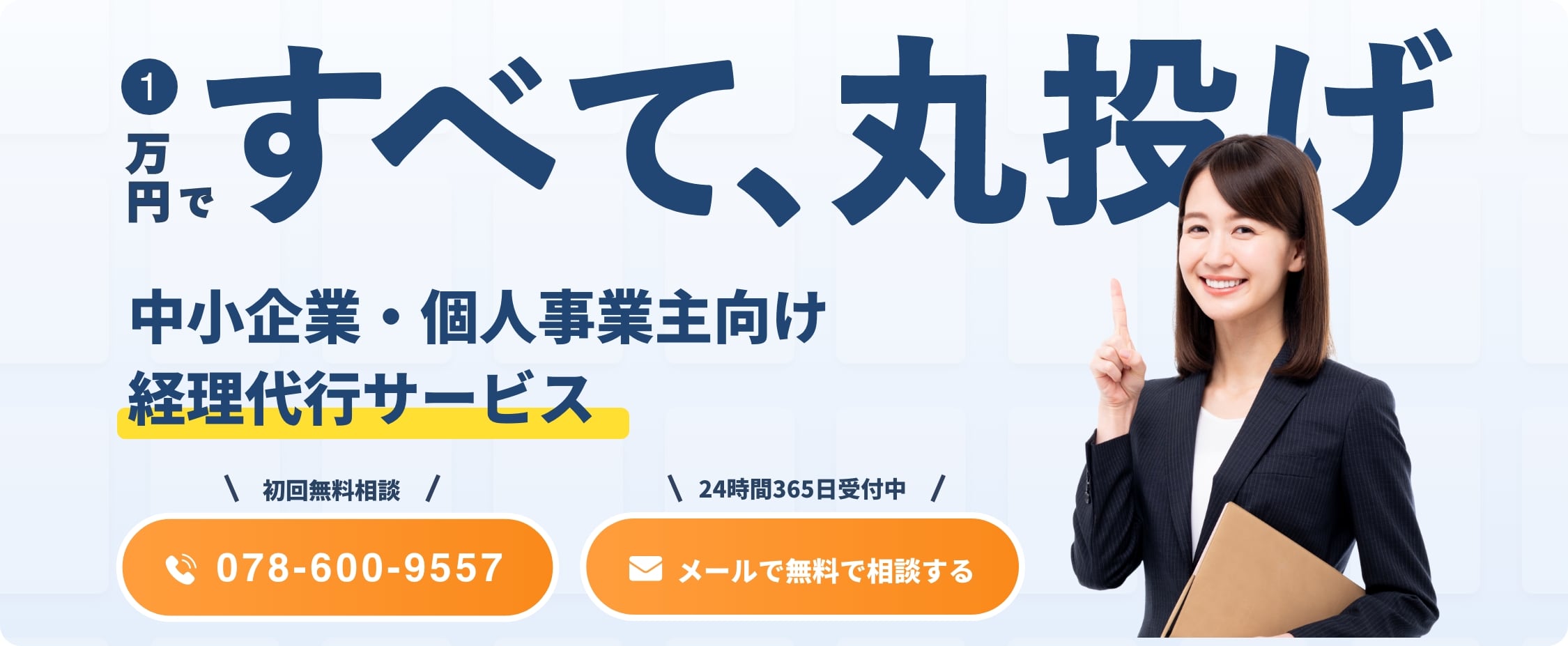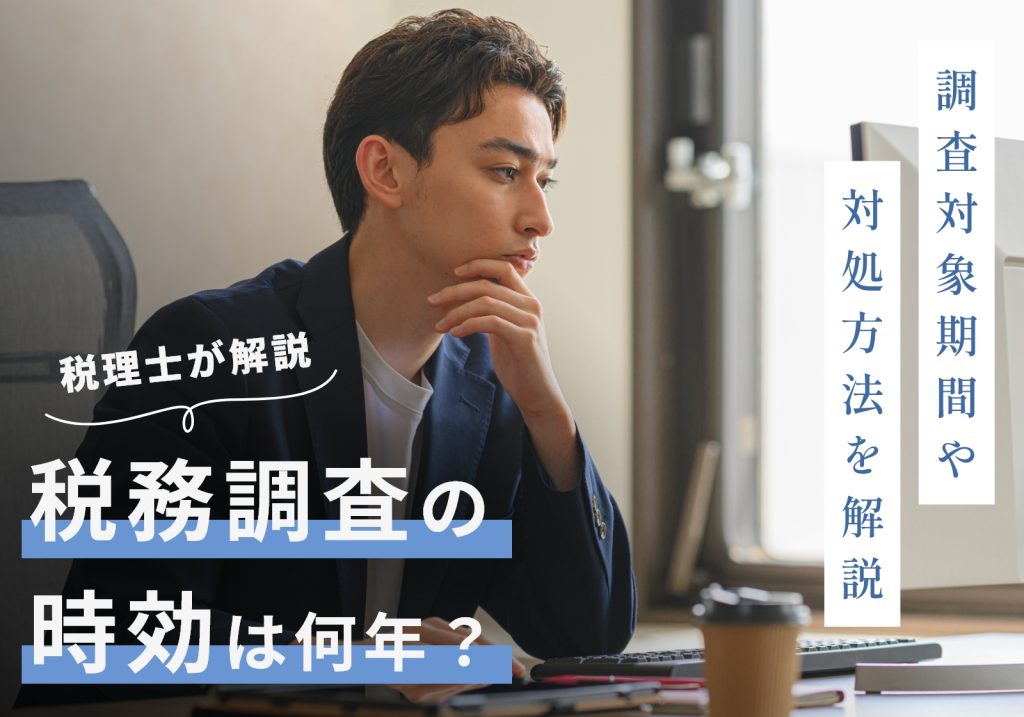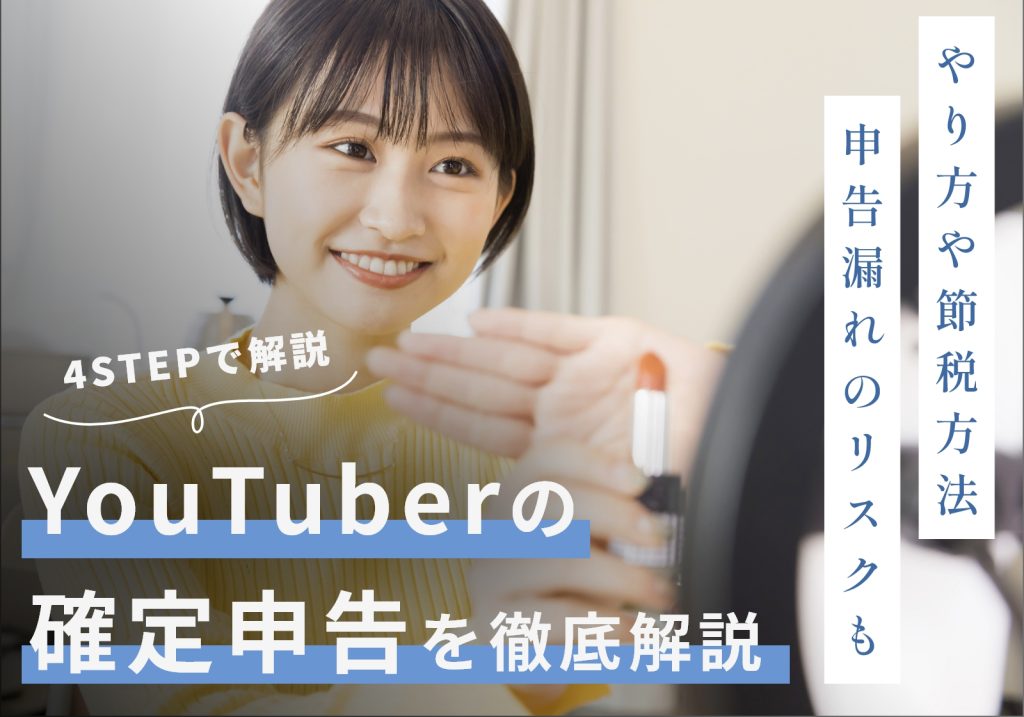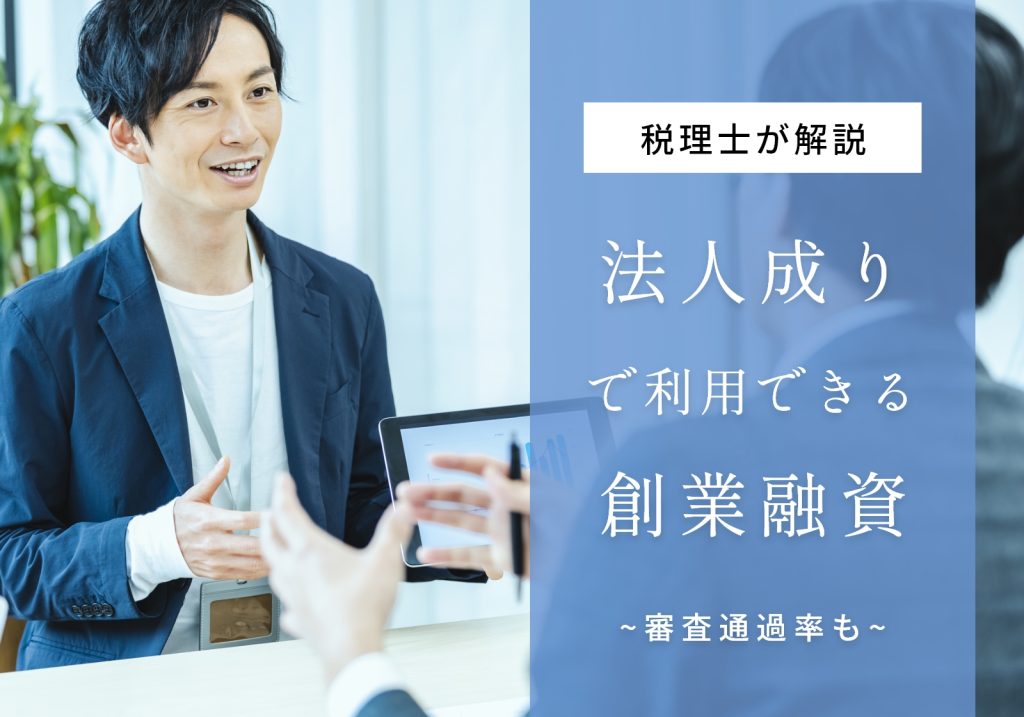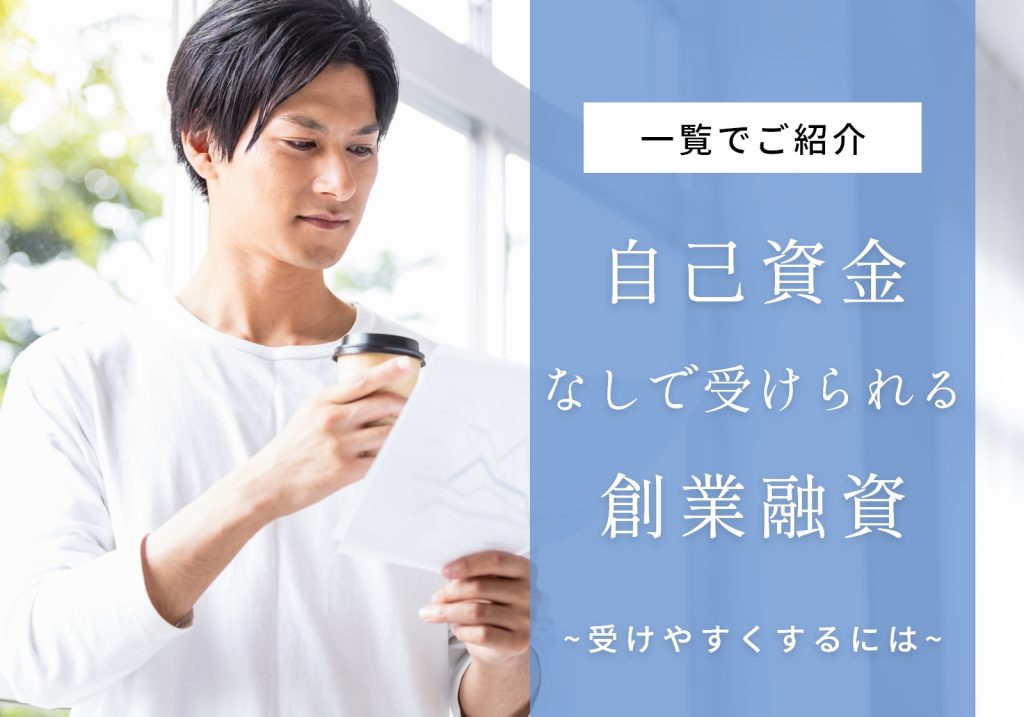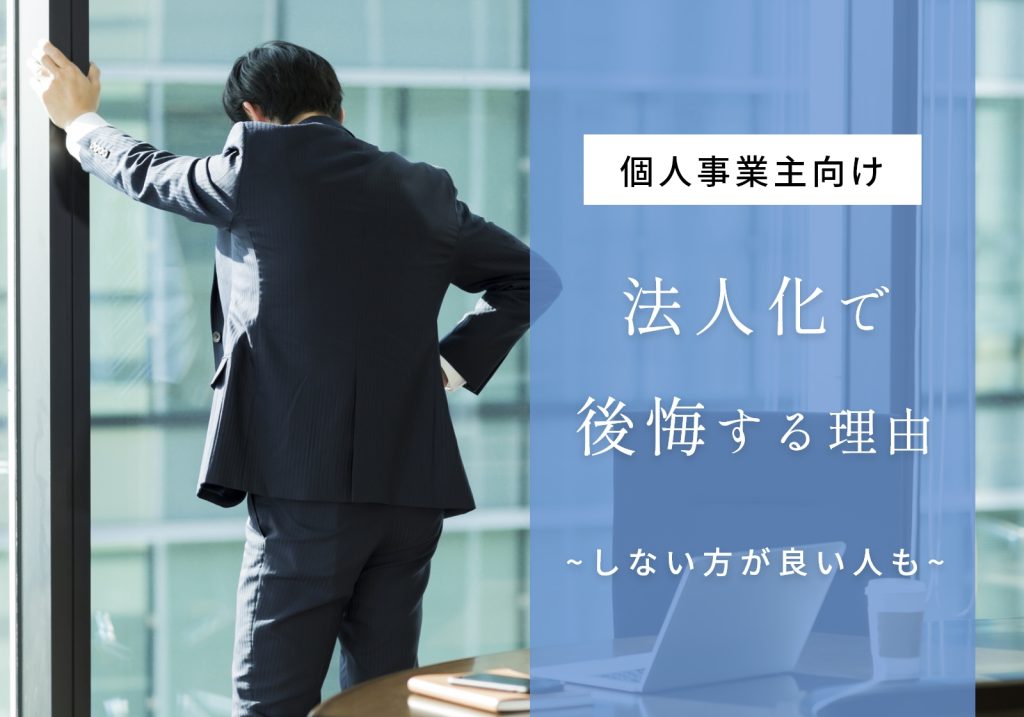
個人事業主の法人化には、節税や赤字の繰越、信用力の向上などさまざまなメリットがあります。
しかし、深く考えず思い切って法人化すると、後悔する可能性もゼロではありません。
「法人化して後悔するくらいであれば、個人事業主のままでいたい」と考える方が大半でしょう。
今回は個人事業主が法人化して後悔する5つの理由や後悔しない年収の目安、法人化しない方が良い人の特徴などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、あなたが現時点で法人化すべきか否かが明確になります。
目次
法人化して後悔する主な理由5選
個人事業主が法人化をして、後悔する主な理由は以下の5つです。
- 会社の設立に想像以上の費用がかかったから
- 稼いだお金を自由に使えないから
- 決算がより大変になったから
- 節税どころか税金が高くなったから
- 赤字なのに税金がかかるから
それぞれ詳しく解説します。
会社の設立に想像以上の費用がかかったから
税務署に開業届を提出すれば、個人事業主として簡単に事業を始められます。費用もかかりません。
一方、法人化の際は最低でも24万円ほどの費用がかかります。内訳は以下のとおりです。
- 定款費用:32,000〜92,000円
- 登記費用:170,000円〜
- 資本金:1円〜
資本金は1円でも構いませんが、信用力の観点から100万円以上とするのが一般的です。
これらの費用は、事業のスタートダッシュ期において、決して小さな負担ではありません。
手軽に始められると思っていたのに、想像以上に費用がかかってしまい、法人化を後悔する方がいます。
関連記事:個人事業主から法人化する際の費用は最低24万円!後悔しないタイミングや年間費用についても紹介
稼いだお金を自由に使えないから
個人事業主は、事業で稼いだお金をすべて自分のものとして使えます。事業用の口座から、生活費を引き出すことも可能です。
しかし法人化すると、会社のお金と個人のお金は法律上、完全に別人格のものとして区別されます。
たとえ社長一人だけの会社でも、私的な目的で自由にお金を引き出すことはできません。
社長が会社からお金を得るためのルートは、毎月決まった額が支払われる役員報酬のみです。
「今月は売上が良かったから少し多めに引き出そう」といった柔軟な対応は、原則として認められません。
正規の手続きを経ずに会社のお金を引き出すと、それは社長が会社からお金を借りた「役員貸付金」として扱われ、融資判断上不利になります。
このようにせっかく稼いだお金を自由に使えず、法人化を後悔する方がいます。
決算がより大変になったから
個人事業主の確定申告も、決して簡単ではありません。特に複式簿記が必要な青色申告をする場合は尚更です。
しかし法人の税務申告は、個人事業主とは比べものにならないほど複雑です。
個人事業主の確定申告は、会計ソフトを使って自力で行うことも不可能ではありませんでした。何年も自力で、負担を感じることなく確定申告をしていた方もいらっしゃるでしょう。
一方で法人の場合は、自力での申告は原則不可能です。税理士への依頼が必須となります。
そして税理士への依頼には、月額2万円からの報酬が必要です。
以上から「自分でなんとかなると思っていたのに、想定外のコストと手間がかかる」と、法人化を後悔する方がいます。
関連記事:青色申告と白色申告の違いとメリット・デメリットを解説
節税どころか税金が高くなったから
法人化の最大の目的として、節税を挙げる方は少なくありません。
たしかに、うまく法人化をすれば節税になります。しかしタイミングを間違えると、節税になるどころか、かえって手元に残るお金が減ってしまいます。
その最大の要因が、社会保険料の負担増です。
個人事業主の場合、社会保険への加入は任意です。しかし法人の場合、社長一人だけの会社であっても強制加入となります。
社会保険料は、会社と個人で折半をします。一人社長の場合、結局は両方とも自身が捻出することになるため、負担が増えるのです。
そしてこの社会保険料の負担は、国民健康保険や国民年金と比べて高額になるケースが多いです。
所得がそれほど高くない段階で焦って法人化すると、この社会保険料を理由に後悔します。
赤字なのに税金がかかるから
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税は課税されません。つまり、利益が出ていなければ税金の負担はゼロになります。
しかし、法人の場合はたとえ事業が赤字であっても、毎年必ず支払わなければならない税金が存在します。それが「法人住民税の均等割」です。
法人住民税は法人税額に応じて課税される「法人税割」と、所得に関係なく資本金の額や従業員数に応じて課税される「均等割」の2つで構成されています。
この均等割は、法人がその地域に存在するだけで課される会費のようなものであり、赤字か黒字かは一切関係ありません。
金額は自治体によって異なりますが、資本金1,000万円以下、従業員50人以下の小規模な会社でも、最低で年間約7万円ほどの納税義務が発生します。
この固定費の存在が、キャッシュフローの厳しい時期には大きな負担となり、「個人事業主のままなら払わなくてよかったのに」という後悔につながります。
法人化して後悔しない年収の目安は?
個人事業主が法人化をしても後悔しない年収の目安は、以下の2つです。
- 売上1,000万円以上
- 所得800万円以上
1つずつ詳しく見てみましょう。
売上1,000万円以上
2年前の売上が1,000万円を超えた事業者は、その年から消費税を納める義務が生じます。
※インボイス制度に登録している場合は、売上規模にかかわらず納税義務が発生します。
しかし、タイミング良く法人化することで、消費税の納税をさらに最大2年間後ろ倒しすることが可能です。
なぜなら新しく設立された法人は、設立1期目と2期目は原則として消費税の納税が免除されるからです。
法人の消費税納税義務も「2期前の売上」と判定されます。
設立したばかりの法人にはその基準となる過去の売上が存在しないため、消費税の支払い義務が生じません。
この仕組みを利用し、個人事業主として売上が1,000万円を超えたタイミングで法人を設立すれば、本来であれば2年後から始まるはずだった消費税の納税負担を先延ばしできます。
所得800万円以上
個人事業主に課される所得税は、所得が増えるほど税率も高くなる累進課税です。
税率は5%からスタートし、所得が増えるにつれて10%、20%と上昇し、最高で45%に達します。
以下は、個人事業主の所得税率をまとめた表です。
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上 | 45% |
一方、法人に課される法人税は、23.2%が原則です。
つまり個人事業主の所得が8,999,000円を上回ると、法人税の方が税率が低くなります。
そのため課税所得800万円を超えたあたりが、法人化を検討する1つの目安とされています。
関連記事:個人事業主が法人化するタイミングは3つ!メリット・デメリットやお得な助成金を紹介
法人化ができない人もいる
法人化は、誰でも望めば必ずできるわけではありません。
まず以下の「法律上の結格事由」に該当する人は、会社の役員になれません。
- 法人そのもの
- 会社法、金融商品取引法、破産法など会社関連法律違反の罪を犯し、刑の執行終了または執行猶予から2年経過していない者
- 上記以外の罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中は除く)
出典:e-Gov 法令検索 会社法331条
また、法律上の問題はなくても、法人設立の費用を捻出できないというケースも少なくありません。
前述のとおり、法人化には最低でも24万円+資本金が必要です。
関連記事:個人事業主から法人化する際の費用は最低24万円!後悔しないタイミングや年間費用についても紹介
あえて法人化をしない方が良い人の特徴
以下のいずれかに当てはまる場合には、法人化をおすすめしません。
- 売上や所得がそれほど高くない人
- 自力で確定申告をしたい人
- 資金を柔軟に使用したい人
それぞれ詳しく見てみましょう。
売上や所得がそれほど高くない人
法人化最大のメリットは節税です。しかし一定以上の所得がなければ、節税効果を十分に受けられません。
例えば「所得が8,999,000円を上回ると、個人事業主の所得税率より法人の法人税率の方が低くなる」とお伝えしました。
年間の所得が500〜600万円以下であれば、むしろ法人化をしない方が良いでしょう。
所得が低い段階で法人化すると、法人住民税の均等割・社会保険料・税理士報酬など、余計に費用がかかります。
所得が800万円を超えたあたりから法人化を検討するのが賢明な判断です。
自力で確定申告をしたい人
個人事業主の確定申告も、決して簡単ではありません。しかし簿記・会計の知識を身につけ、会計ソフトを活用すれば、自力での確定申告も可能です。
一方、法人になると自力での確定申告は非現実的です。税理士への依頼が欠かせません。
そのため、確定申告や帳簿付けといった経理作業を、自分自身で管理・把握したいのであれば、無理に法人化をする必要はありません。
しかし法人化をして確定申告を税理士に依頼しても、書類や税理士との打ち合わせによって、お金の動きは把握できます。
「税理士に依頼すると、お金の流れがブラックボックス化するのでは?」といった心配は不要です。
資金を柔軟に使用したい人
法人化すると、前述のとおり会社のお金と個人のお金は完全に別人格として扱われます。社長であっても、会社のお金を自由に使うことはできません。
そのため「売上は増えたのに、自由に使えるお金は個人事業主の頃と変わらない」「むしろ少なく感じる」といった悩みを抱える方も少なくありません。
売上が数千万円に達する場合は、節税の観点から法人化をした方が良いでしょう。
しかし、法人化の目安である売上1,000万円や所得800万円付近では、あえて法人化をしないという選択肢もあります。
迷う場合には「法人化すべきか」を税理士に相談するのも選択肢の1つです。
法人化で後悔しないために意識すること
法人化をして後悔したくないのであれば、以下の3点を押さえておきましょう。
- 無理に法人化する必要はない
- 創業融資についてきちんと調べる
- 税理士のサポートを受ける
1つずつ詳しく解説します。
無理に法人化する必要はない
法人化は、事業を成長させるための手段です。法人化自体が目的になってはいけません。
「周りが法人化し始めたから」「なんとなくカッコいいから」のような漠然とした理由で、無理に法人化すると後悔します。
法人化をすれば、多くのコストや義務が生じます。その負担に見合うだけのメリットがあると判断できなければ、無理に法人化する必要はありません。
創業融資についてきちんと調べる
法人化をする際、多くの人が資金調達の方法として創業融資を検討します。
しかし創業融資には「事業開始後〇年以内でなければ利用できない」といった条件が設けられているのが一般的です。
この事業開始時点は、法人の設立日ではありません。個人事業を開始した時点から通算して判断されます。
「法人化後に創業融資を利用できないと判明して後悔する」といった事態を避けるためにも、事前のリサーチが欠かせません。
詳しくは以下の記事でも解説しています。
関連記事:法人成りで利用できる創業融資を解説!審査通過率を高める方法も
税理士のサポートを受ける
法人化には、税務・法務・社会保険など、さまざまな専門知識が求められます。そのため、税理士への相談がおすすめです。
税理士に相談すれば、役員報酬をいくらにすべきか、そもそも法人化すべきかといった、さまざまなアドバイスを受けられます。法人化に伴う後悔がなくなるでしょう。
関連記事:税理士に会社設立を相談する際の費用相場は0〜5万円!そもそも必要なのか、相談しないで良いパターンも紹介
後悔しない法人化は永安栄棟税理士事務所にお任せください
永安栄棟税理士事務所では、弊所のお客様向けに、起業時の「開業支援」サービスを無料で提供しています。具体的なサポート内容は以下のとおりです。
- 設立支援:必要な届出書の作成や司法書士・社労士の紹介など
- 資金調達支援:資金調達方法に関するアドバイス
- 設立時の運営指導:役員報酬の金額や合同会社・株式会社の選択などのアドバイス
また個人事業主や中小企業向けの「確定申告丸投げパック」を提供しています。
サービス内容は以下のとおりです。
- 日々の会計帳簿の記帳
- 決算書の作成
- インボイスへの対応
- 消費税申告書の作成
- 確定申告書の作成
料金は以下のとおりです。
| 売上規模 | 月額報酬(毎月) | 決算報酬(年1回) |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 1万円(個人) 2万円(法人) | 2万円(個人) 12万円(法人) |
| 〜2,000万円 | 2万円(個人) 2.5万円(法人) | 12万円(個人) 16万円(法人) |
| 〜3,000万円 | 3万円 | 16万円 |
| 〜4,000万円 | 4万円 | 18万円 |
| 5,000万円超 | ご相談 | ご相談 |
弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。ぜひ以下より、各プランについて詳しく見てみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる
まとめ
個人事業主が法人化して後悔する5つの理由や後悔しない年収の目安、法人化しない方が良い人の特徴などについて解説しました。
売上や所得が増えるほど、法人化によるメリットも大きくなります。
法人化によるメリットと、後悔する可能性を天秤にかけて判断しましょう。
法人化すべきか悩む場合、法人化の手続き、法人化後の確定申告などについては、税理士のサポートがおすすめです。
弊所のサービスについては、以下よりチェックしてみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる