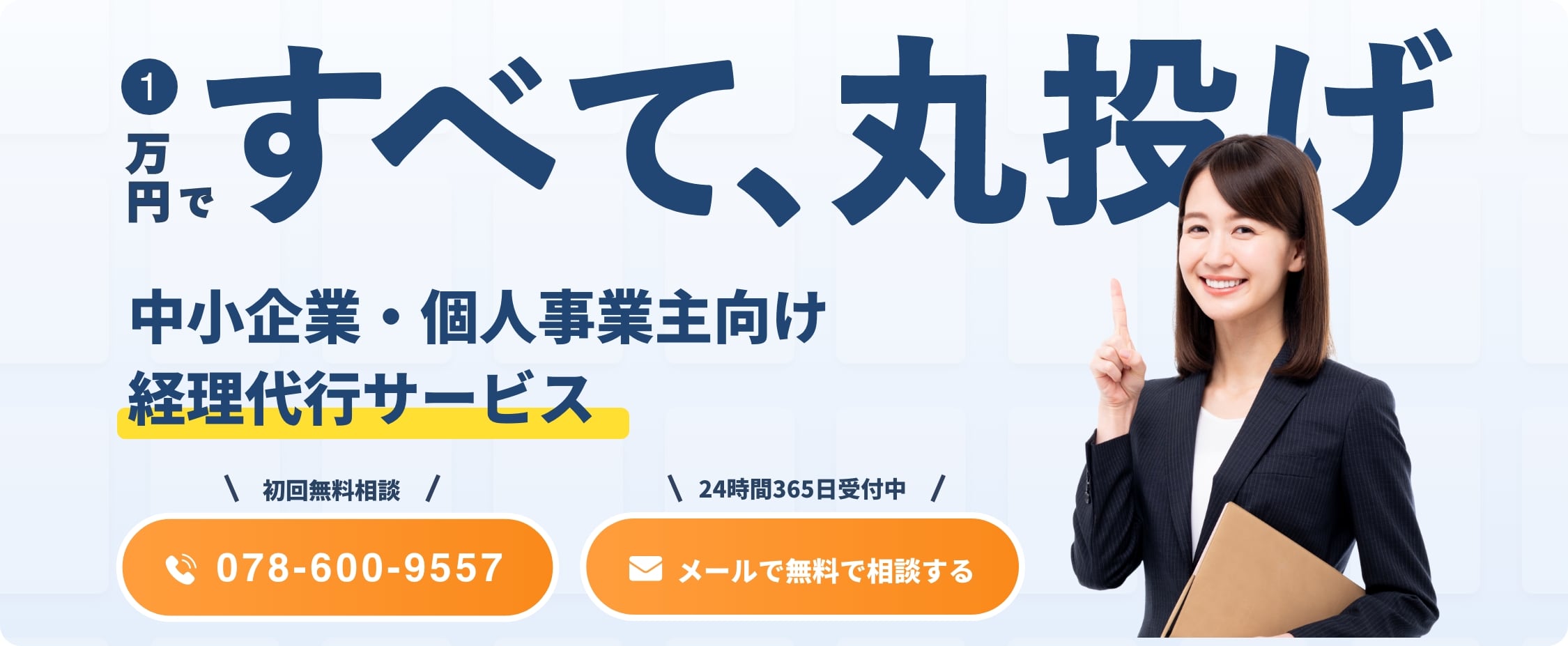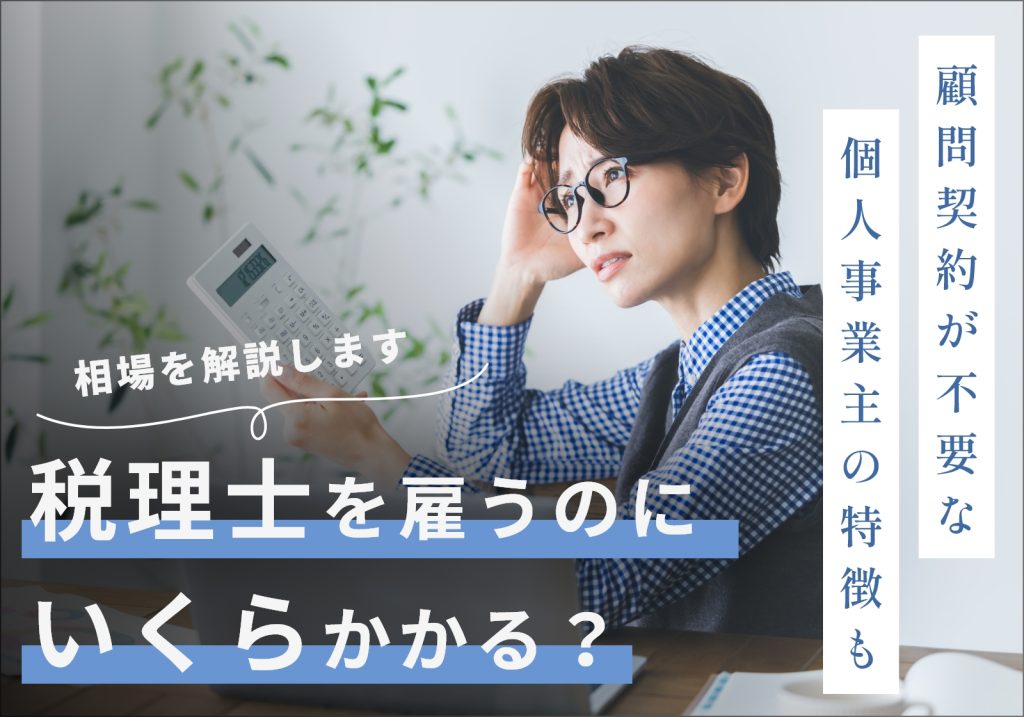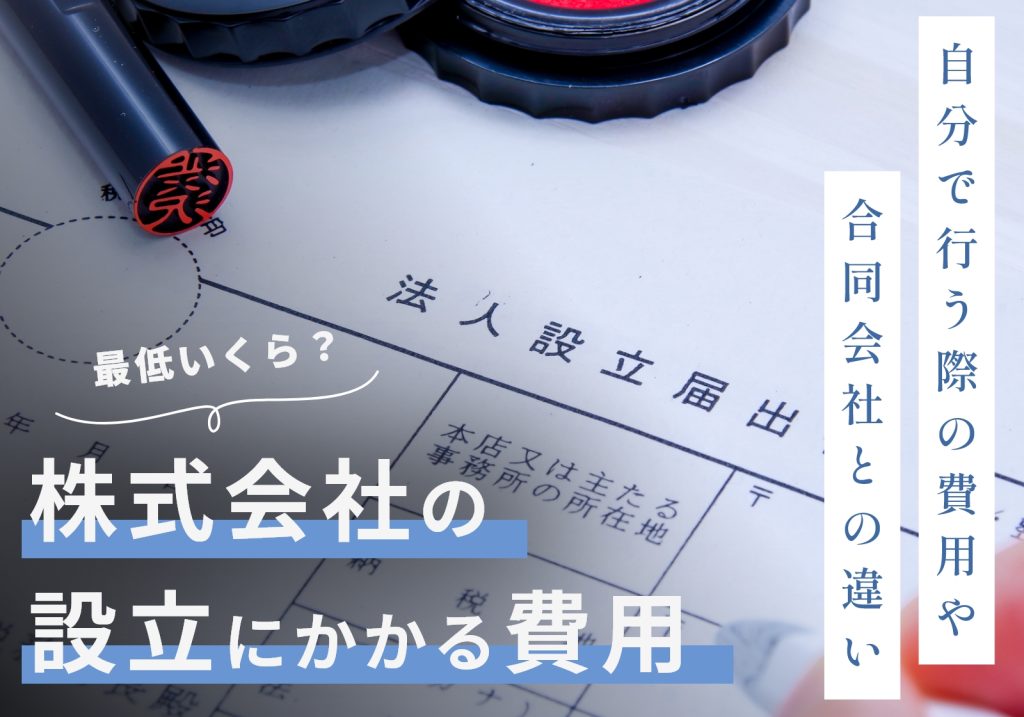
株式会社の設立には、最低24万円の費用がかかります。最低12万円ほどで設立できる合同会社と比べると、倍近い費用がかかります。
そして株式会社の設立にかかった費用の一部は、経費として計上可能です。
「株式会社の設立を検討しており、かかる費用について知りたい」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
今回は株式会社の設立にかかる費用の内訳や設立後にかかる年間費用、株式会社と合同会社における設立費用の違いなどについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、株式会社の設立に向けて一歩前進できます。
目次
株式会社を自分で設立する際にかかる費用は最低24万円
個人事業主は、開業届を提出すれば無料で事業を始められます。
一方、株式会社の設立には費用が必要です。
専門家のサポートを受けずに、すべて自分で手続きを行った場合、株式会社の設立には最低24万円の費用がかかります。
「自分でやれば安く済む」と考える方も多いでしょう。
しかし、あくまで専門家への「代行手数料」がかからなくなるだけで、国や役所などに支払う費用は一切変わりません。
株式会社の設立にかかる費用の内訳
株式会社の設立にかかる費用の内訳は、以下のとおりです。
- 定款費用(32,000〜52,000円)
- 登記費用(170,000円〜)
- 資本金(1円〜)
それぞれ詳しく解説します。
定款費用(32,000〜52,000円)
定款(ていかん)とは、会社の基本的なルールを定めた「会社の憲法」とも言える重要な書類です。
この定款を作成し、その内容が正当なものであることを国に証明してもらう手続きに費用がかかります。費用の内訳は、以下のとおりです。
| 内訳 | 費用 |
|---|---|
| 認証手数料 | 30,000〜50,000円 |
| 謄本代 | 2,000円程度 |
| 収入印紙代 | 40,000円 |
| 印鑑証明書 | 300円 |
まず、作成した定款が法的に有効なものであることを公証人に証明してもらうための「認証手数料」として、資本金の額に応じて3〜5万円が必要です。
加えて、完成した定款の謄本(写し)を発行してもらうための「謄本手数料」が、1ページあたり250円(通常は8ページ前後で約2,000円)かかります。
ここで注意が必要なのが、紙で定款を作成した場合にかかる「収入印紙代」4万円です。
しかし、専用の機器やソフトを導入し「電子定款」というデータ形式で認証を受ければ、この収入印紙代は不要になります。
自分でその環境を整えるにはコストと手間がかかるため、この部分は専門家に依頼するメリットが大きいと言えます。
登記費用(170,000円〜)
定款の準備が整ったら、次に行うのが法務局へ会社を設立したことを届け出る「法人登記」です。
この登記手続きにかかる税金が「登録免許税」で、株式会社の設立において最も大きな費用となります。
登録免許税の額は「資本金の額×0.7%」で計算されます。しかし、その金額が15万円に満たない場合は、一律で15万円を納めなければなりません。
資本金が約2,100万円を超えるまでは、この最低額である15万円がかかると考えてよいでしょう。
また、登記手続きには会社の印鑑の作成も必要です。印鑑の作成には、2万円近くかかります。
登記にかかる費用の内訳は、以下のとおりです。
| 内訳 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税 | 資本金×0.7%か15万円の高い方 |
| 会社実印費用 | 20,000円〜 |
資本金(1円〜)
資本金は、会社の事業運営の元手となる資金です。設立時に会社に払い込みます。
会社法上は、資本金1円でも問題ありません。しかし、資本金1円での設立はデメリットが非常に多く、おすすめできません。
なぜなら、資本金は会社の「信用力」や「体力」を示すバロメーターだからです。
資本金が極端に少ないと、銀行から法人口座の開設や、融資を断られたりする可能性が高くなります。
また、取引先からも支払い能力を不安視され、契約に至らないケースも出てくるでしょう。
明確な基準はありませんが、少なくとも50万円以上の資本金は用意したいところです。
資本金の決め方については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:会社の設立に必要な資本金の決め方!平均や最低金額についても解説
関連記事:銀行の法人口座開設を断られる理由は?開設できないとどうなるか、対処法を紹介
関連記事:個人事業主から法人化する際の費用は最低24万円!後悔しないタイミングや年間費用についても紹介
株式会社よりも合同会社の方が設立費用は安い
株式会社の設立には、最低24万円かかります。一方、合同会社は12万円ほどで設立が可能です。
まず、合同会社は株式会社と異なり、公証役場での定款認証が不要です。これにより、株式会社で必須だった認証手数料(3〜5万円)が丸々かかりません。
そして、最も大きな違いが法務局に支払う登録免許税です。株式会社が最低でも15万円かかるのに対し、合同会社の登録免許税は最低6万円で済みます。
しかし、設立費用の違いだけで株式会社か合同会社かを判断すべきではありません。判断基準については、弊所でもアドバイスが可能ですので、ぜひお問い合わせください。
関連記事:合同会社に税理士は必要!費用相場や「いらない」が間違いである理由を解説
株式会社の設立後にかかる主な年間費用
株式会社の設立後にかかる主な費用は、以下のとおりです。
- 税金
- 社会保険料
- 税理士や弁護士への報酬
1つずつ詳しく見てみましょう。
税金
会社を設立すると、個人事業主とは異なるさまざまな税金を納める義務が生じます。
具体的には、会社の利益(所得)に対して課される「法人税」、そして都道府県や市町村に納める「法人住民税」や「法人事業税」などがあります。
利益が出ていれば、当然これらの税金を支払わなければなりません。
しかし「法人住民税の均等割」は、会社の所得が赤字であっても支払わなければなりません。
資本金1,000万円以下、従業員50人以下の小規模な会社でも、最低で年間約7万円の納税義務が生じます。
個人事業主時代は赤字なら税負担がゼロでした。そのため、この固定コストの存在は大きな違いとなります。
社会保険料
法人を設立すると、社長一人の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられます。
社会保険料は、会社と役員・従業員がそれぞれ約半分ずつを負担します。この会社負担分の社会保険料は、経営における非常に大きな固定費となるでしょう。
従業員が増えるほど、社会保険料の負担は大きくなります。
また、一人企業の場合、個人負担分も会社負担分も実質的には自身で支払っているようなものです。
役員報酬の金額にもよりますが、報酬額のおおよそ15%程度が会社負担分として毎月発生します。
例えば役員報酬を月額30万円に設定した場合、会社は約4.5万円の社会保険料を別途負担しなければなりません。
この負担増は、法人化の際に節税メリットと天秤にかけるべき重要なポイントです。
税理士や弁護士への報酬
法人の税務申告は、個人事業主の確定申告とは比較にならないほど複雑です。
個人事業主の場合、専門知識があれば自力での確定申告も可能でした。しかし株式会社の税務申告は、税理士への依頼が原則です。
そして税理士との顧問契約には、月数万円の顧問料が必要です。
また、事業を運営していく上では、取引先との契約トラブルや労務問題など、法的な判断が必要になる場面も出てきます。
そのような際に、弁護士に相談するための相談料や顧問料も、必要に応じて発生します。
税理士への依頼にかかる費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:税理士を雇う(顧問契約を結ぶ)のにいくら必要?個人事業主が確定申告の依頼にかかる費用を紹介
株式会社の設立にかかった費用は経費になる?
株式会社の設立にかかった法定費用や専門家への手数料は、全額経費として計上可能です。
しかし通常の経費のように、支出した年に一度に計上するわけではありません。
これらの設立費用は、会計上「創立費」という特殊な勘定科目で処理され、「繰延資産(くりのべしさん)」として扱われます。
繰延資産とは、その支出の効果が将来にわたって及ぶと考えられる費用を、一旦資産として計上し、その後数年間にわたって少しずつ経費化(償却)していくものです。
そして、この「創立費」の大きな特徴は、「任意償却」が認められている点です。
任意償却では、「いつ、いくら経費にするか」を会社が自由に決められます。
例えば、設立初年度が赤字であれば経費化せず、利益が大きく出た2年目や3年目に全額を経費として計上し、利益を圧縮して法人税を節税する、といった戦略的な使い方が可能です。
株式会社の設立を司法書士に依頼する際にかかる費用
株式会社の設立手続きには、定款作成や登記申請など、専門的な知識が求められます。
これらの手続きを自分で行うことも可能ですが、時間と手間がかかる上、ミスがあればやり直しとなり、かえってコストがかかる可能性もあります。
そのため、登記手続きの専門家である司法書士に設立を依頼するのが一般的です。
司法書士に株式会社の設立を依頼した場合の報酬相場は、5〜10万円程度です。これに、前述した最低24万円の費用が加わります。
株式会社の設立は税理士事務所への依頼もおすすめ
会社の設立手続きは、司法書士の独占業務です。
そして税理士事務所のなかには、司法書士と連携して、株式会社の設立サポートを提供しているところもあります。
株式会社を設立したあとは、いずれにせよ税務申告のために、税理士と顧問契約を結びます。
自社にあった司法書士を探して、税理士事務所も探すのは大変です。
会社の設立を、司法書士と連携する税理士事務所に相談すれば、顧問契約を結ぶ税理士を後から探す必要がありません。
関連記事:起業したら税理士は必要?不要?費用や相談時に聞くことを解説
株式会社の設立は永安税理士事務所におまかせください
永安栄棟税理士事務所では、弊所のお客様向けに、起業時の「開業支援」サービスを無料で提供しています。具体的なサポート内容は以下のとおりです。
- 設立支援:必要な届出書の作成や司法書士・社労士の紹介など
- 資金調達支援:資金調達方法に関するアドバイス
- 設立時の運営指導:役員報酬の金額や合同会社・株式会社の選択などのアドバイス
また個人事業主や中小企業向けの「確定申告丸投げパック」を提供しています。
サービス内容は以下のとおりです。
- 日々の会計帳簿の記帳
- 決算書の作成
- インボイスへの対応
- 消費税申告書の作成
- 確定申告書の作成
料金は以下のとおりです。
| 売上規模 | 月額報酬(毎月) | 決算報酬(年1回) |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 1万円(個人) 2万円(法人) | 2万円(個人) 12万円(法人) |
| 〜2,000万円 | 2万円(個人) 2.5万円(法人) | 12万円(個人) 16万円(法人) |
| 〜3,000万円 | 3万円 | 16万円 |
| 〜4,000万円 | 4万円 | 18万円 |
| 5,000万円超 | ご相談 | ご相談 |
弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。ぜひ以下より、各プランについて詳しく見てみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる
まとめ
株式会社の設立にかかる費用の内訳や設立後にかかる年間費用、株式会社と合同会社における設立費用の違いなどについて解説しました。
株式会社の設立には、最低24万円の費用がかかります。なお、資本金をきちんと用意する場合には、さらに50〜100万円ほどの費用が必要です。
株式会社設立のメリットと、かかる費用などを天秤にかけ、どのような選択をすべきか考えましょう。
株式会社を設立すべきか悩む場合、設立の手続き、設立後の税務申告などについては、税理士のサポートがおすすめです。
弊所のサービスについては、以下よりチェックしてみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる