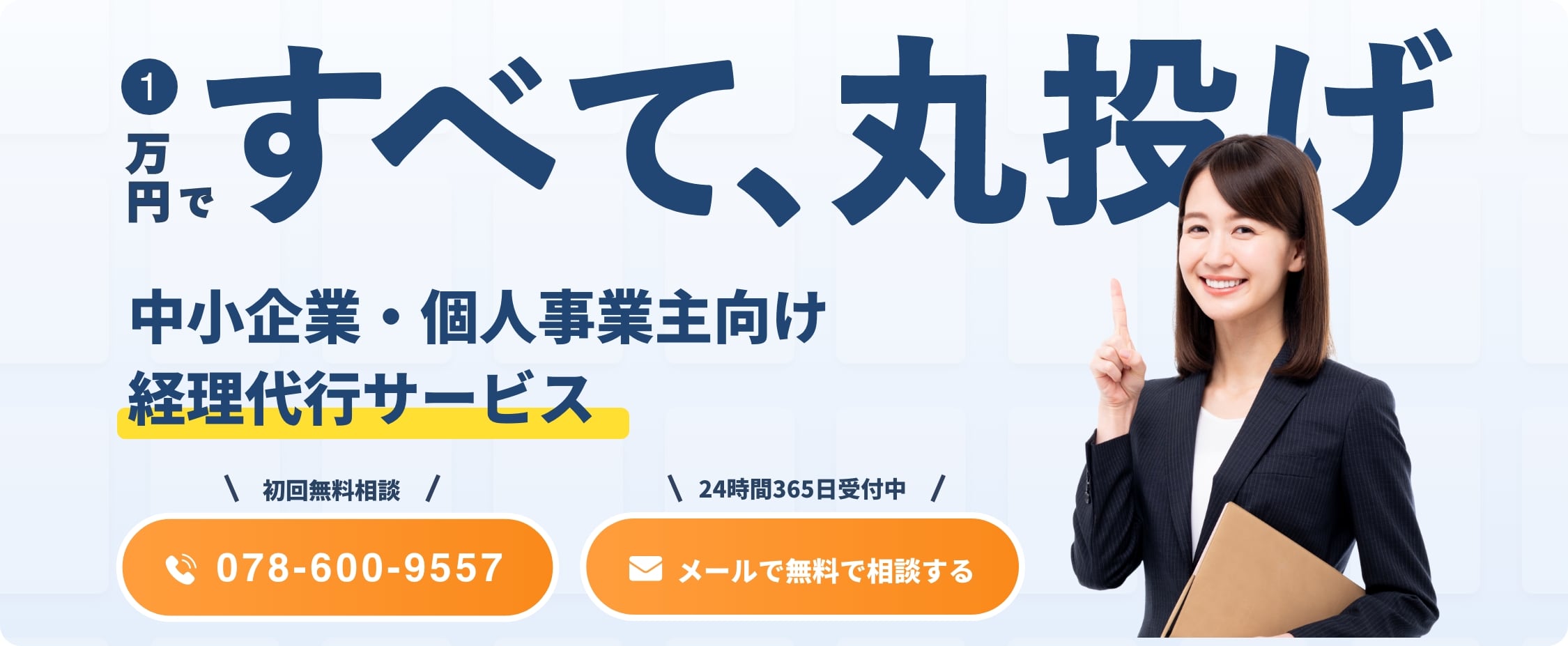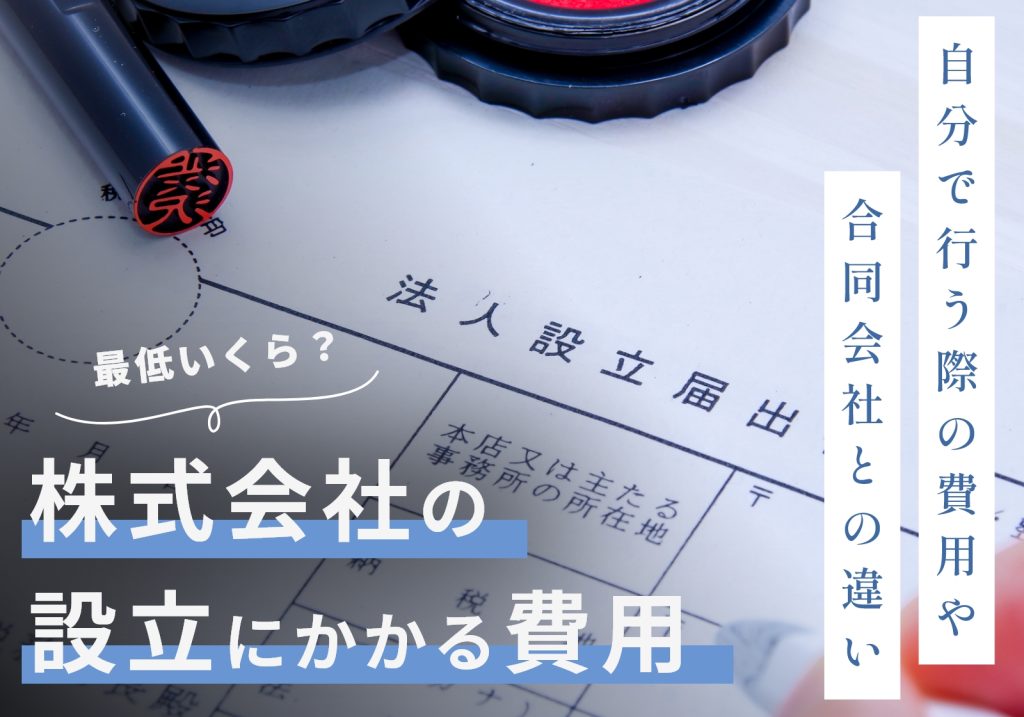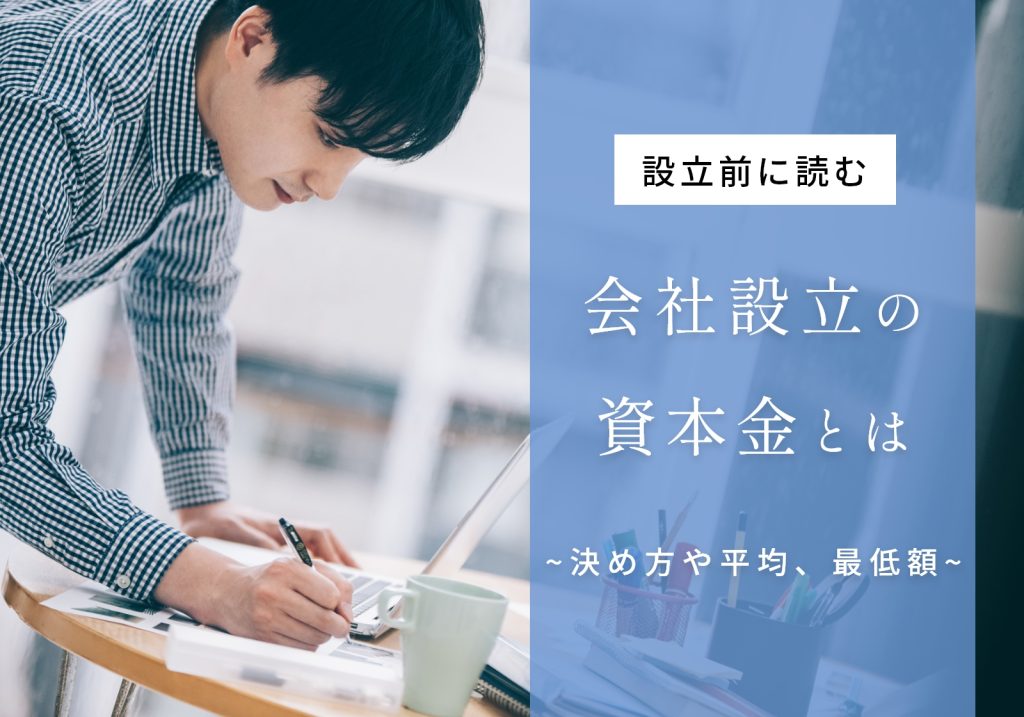
会社の設立には、資本金が必要です。そして資本金の額は1円からとなっています。
しかし資本金を1円にすると、さまざまなデメリットがあるためおすすめできません。少なくとも50万円、できれば100万円以上をおすすめします。
また、中小企業の資本金額の平均は、300〜500万円です。
今回は、会社の設立に必要な資本金の決め方や1円での設立をおすすめしない理由、資本金の平均額などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、会社の設立に向けて一歩前進できます。
目次
【前提】株式会社も合同会社も設立には資本金が必要
資本金は、会社の設立形態が株式会社であっても合同会社であっても必要です。
資本金と聞いて「会社にストックしておかなければならないお金」といったイメージを抱く方も多いでしょう。
しかし、資本金は会社の財産として自由に使用可能です。具体的には、事務所の契約費用や備品の購入、当面の運転資金などに充てられます。
また、資本金は単なる運転資金ではありません。会社の「体力」や「規模」を示す重要な指標となります。
会社の登記簿謄本に金額が記載され、誰でも閲覧できるため、金融機関や取引先がその会社の信用力を判断する際の客観的な材料となります。
会社設立時の資本金は最低1円から
かつては、株式会社の設立に最低1,000万円の資本金が必要でした。
しかし2006年に最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも株式会社や合同会社を設立できるようになりました。
これは、手元資金が少ない人でも起業に挑戦しやすくするための規制緩和の一環です。
そして「法律上可能であること」と「実務上それが適切であるか」は別の話です。
資本金1円という手軽さは、魅力的に映るでしょう。
しかしその裏側には、会社の信用力を著しく損ない、事業のスタートダッシュでつまずく原因となる、数多くのデメリットが存在します。
なぜ資本金1円での設立が推奨されないのか、その具体的な理由については、次の章で詳しく解説します。
資本金1円での会社設立はおすすめしない
以下3つの理由から、資本金1円での会社設立はおすすめしません。
- 法人口座開設の審査に通りにくくなるから
- 会社の信用力が得られないから
- 会社の設立に「覚悟」がいらないから
それぞれ詳しく解説します。
法人口座開設の審査に通りにくくなるから
資本金1円で会社を設立すると、銀行の法人口座開設の審査に通りにくくなります。
法人口座は取引先からの入金や経費の支払い、そして将来的な融資を受けるための必須のインフラです。この入り口でつまずいてしまえば、事業は事実上スタートできません。
銀行は、マネーロンダリングや詐欺といった金融犯罪への利用を防ぐため、実態のないペーパーカンパニーとの取引を警戒しています。
審査の過程で、資本金は「事業を継続する体力と意思があるか」を判断する、客観的で分かりやすい指標となります。
資本金が1円の会社は、銀行から以下のように判断され、審査で落とされる可能性が極めて高くなるでしょう。
- 事業を真面目に行う意思がなく、不正な目的で設立されたのではないか
- すぐに資金ショートして口座が犯罪に使われるリスクがある
関連記事:銀行の法人口座開設を断られる理由は?開設できないとどうなるか、対処法を紹介
会社の信用力が得られないから
資本金は、会社の登記簿謄本に記載され、誰でも閲覧できる公的な情報です。会社の「体力」や「事業への本気度」を外部に示す、分かりやすい信用力のバロメーターです。
もし、あなたの会社の資本金が1円だった場合、取引先や金融機関はどう感じるでしょうか。
「この会社は事業を継続する体力があるのか?」「支払い能力に問題があるのではないか?」といった疑念を抱かれるでしょう。
信用力がゼロに等しいと評価されても仕方がありません。
特に、BtoBビジネスでは、取引を開始する前に相手の信用力を調査するのが一般的です。
その際に資本金の額を基準にしている企業も少なくなく、1円では門前払いされてしまう可能性すらあります。
会社の設立に「覚悟」がいらないから
精神論に聞こえるかもしれませんが、「覚悟」の度合いも、事業を継続していく上で重要なポイントです。
資本金1円という、いわば「ノーリスク」で始めた事業は、困難に直面した際に「うまくいかないから、もうやめてしまおう」と諦める決断を下しやすくなります。
撤退への心理的なハードルが極めて低いのです。
一方で、自分自身でコツコツ貯めた100万円、300万円といったまとまった資金を資本金として投じている場合、そのお金を失いたくないという強い思いから、事業に対する「覚悟」や「執着心」が生まれます。
この精神的な思いの強さが、困難を乗り越えるための粘り強さや、知恵を生み出す原動力となるのです。
資本金とは、経営者自身が事業成功へ向けてどれだけの覚悟を持っているかを、自分自身に示すためのものでもあります。
会社設立時の資本金の平均は?
会社設立時の資本金の平均は、中小企業の場合300〜500万円ほどとされています。次いで多いのが、資本金300万円以下です。
一般的に、初期費用や仕入れなどの原価がかかる業種ほど、資本金が高い傾向にあります。
しかし、最適な資本金の額は企業ごとに異なります。そのため、平均に惑わされず、自社にあった資本金額を見極めることが重要です。
資本金の決め方については、次の章で詳しく解説します。
会社の設立に必要な資本金の決め方
会社の設立に必要な資本金の決め方は、以下の3つです。
- 許認可を得るのに必要な基準資産額を参考にする
- 創業融資の条件を参考にする
- 取引先の規模を参考にする
1つずつ詳しく見てみましょう。
許認可を得るのに必要な基準資産額を参考にする
あなたの事業が、行政からの許認可を必要とする業種である場合、許認可の取得に必要な基準資産額を参考に資本金の額を決めましょう。
例えば、一般建設業許可を得るには、500万円以上の純資産が必要です。
また、一般労働者派遣事業の許可を得るには、基準資産額が、1事業所あたり2,000万円以上必要です。
さらに、一般旅行業の登録には、3,000万円の基準資産額が求められます。
これらの許認可が必要な事業を始める場合、設立時の資本金をこの基準資産額以上に設定しておけば、設立後すぐに許認可申請を行えます。
創業融資の条件を参考にする
会社設立と同時に、日本政策金融公庫などから創業融資を受けたいと考えている方も多いでしょう。
創業融資には審査があります。そして資本金の額は、融資審査において重要な要素となります。
資本金は「自己資金」として、事業に対する経営者の本気度と、計画性を示すものと見なされるからです。
明確なルールはありませんが、一般的に融資希望額の3分の1から2分の1程度の自己資金(資本金)があると、審査が有利に進むとされています。
例えば、600万円の融資を受けたいのであれば、200〜300万円の資本金を用意するのが理想的です。
自己資金がほとんどない状態で高額な融資を申し込むと、「他人資本に頼りすぎている」と見なされ、審査通過が難しくなるでしょう。
また、資本金が高すぎると、自己資金が潤沢であると判断され、融資が不要と見なされて融資額が減額されるケースもあります。
関連記事:創業融資は税理士がいると安心!成功報酬の相場は3〜5%!依頼内容などについて解説
取引先の規模を参考にする
資本金は、あなたの会社の「信用力」を外部に示す重要な指標です。
そのため、取引をしたいと考えている相手の企業規模を考慮して、資本金額を決める方法もおすすめです。
例えば、主な取引先が個人の消費者や小規模な事業者であれば、資本金の額はそれほど重要ではありません。
しかし、もしあなたが大手企業や官公庁と取引をしたいと考えているのであれば、相手方は契約前に必ずあなたの会社の信用力を調査します。
資本金が数十万円程度だと、支払い能力や事業の継続性を不安視され、取引の土俵にすら上がれない可能性があります。
一般的に、BtoBビジネスでは、最低でも100万円、できれば300万円程度の資本金があった方が、信用を得やすいと言えるでしょう。
会社設立時の資本金払込とは?
資本金の払込とは、会社の設立手続きの一環として、発起人が定款で定めた資本金の額を、指定された金融機関の口座に振り込む行為を指します。
具体的な払込の時期は「定款の認証が終わった後」のタイミングです。
まだ法人口座は存在しないため、振込先は創業者個人の銀行口座の中から一つを選んで使用します。
その後は振込記録が記載された通帳のページをコピーし、法務局に提出する「払込証明書」を用意しましょう。
これらの書類が、資本金が払い込まれたことの証明となり、法人登記申請の添付書類となります。
会社設立時の資本金に見せ金を使うのは違法
「見せ金」とは、資本金を払い込む際に他人から一時的に資金を借り入れ、登記が完了したらすぐに返済して、あたかも自己資金が潤沢であるかのように見せかける行為を指します。
例えば、友人から100万円を借りて資本金の払込を行い、登記完了後にその100万円を引き出して友人に返済する、といったケースです。
見せ金は、会社法で禁止されている違法行為です。見せ金が発覚した場合、その登記は無効となる可能性があります。
さらに、見せ金と類似した違法行為に「預合い」があります。
預合いは、金融機関と結託し、借入金を使って資本金の払込を行い、登記後もその借入金を返済するまで会社が資金を引き出せないように拘束する行為です。
これも見せ金と同様に、会社法で禁じられています。
資本金の決め方を含めた起業時の決め事は税理士への相談がおすすめ
以下3つの理由から、資本金の決め方を含めた起業時の決め事は、税理士への相談がおすすめです。
- 税金や社会保険料を最小化できるから
- 将来の税務リスクを未然に防げるから
- 会社設立後はいずれにせよ税理士への依頼がマストだから
それぞれ詳しく見てみましょう。
税金や社会保険料を最小化できるから
起業時に決める資本金の額や、経営者自身に支払う「役員報酬」の金額は、将来の税金や社会保険料の負担額に影響します。
例えば、役員報酬を高くすれば会社の利益が減り法人税は下がりますが、個人の所得税と社会保険料が上がります。低くすればその逆です。
最適なバランスは、専門家でなければ算出できません。
税理士に相談すれば、「会社と個人のトータル手取り額」が最大化される、最適な役員報酬の金額や資本金の額に関するアドバイスを受けられます。
この初期設定を誤ると、年間で数十〜数百万円単位の損失を被る可能性があります。
将来の税務リスクを未然に防げるから
会社設立時の初期設定は、将来の税務調査で指摘を受けるリスクとも密接に関わっています。
例えば、定款の事業目的に関連性のないものを多数記載したり、事業規模に対して不相当に高額な役員報酬を設定したりすると、税務調査で以下の指摘を受ける原因となるでしょう。
- 事業の実態が不明確である
- 役員報酬が過大である
税理士は、これまでの経験から税務調査官がどのような点をチェックするかを熟知しています。
そのため、設立段階から、後々税務上の問題とならないような、クリーンで合理的な初期設定ができます。
関連記事:税理士に税務調査を依頼する際に知っておくべきことを1から10まで解説
会社設立後はいずれにせよ税理士への依頼がマストだから
個人事業主の確定申告とは異なり、法人の税務申告は複雑です。そのため、会社を設立すれば原則として、税理士に税務申告を依頼することとなります。
設立後に税理士へ依頼するよりも、会社の設立段階から相談をした方が合理的です。
設立前から依頼することで、税理士はあなたの事業内容や将来のビジョンを深く理解した上で、最適な法人設計を提案できます。
そして、設立後はスムーズに会計・税務のサポートに移行できるため、経営者は安心して事業運営に集中できます。
設立手続きだけを他の専門家に依頼し、後から慌てて税理士を探すよりも、一貫したサポートが受けられるメリットは計り知れません。
関連記事:税理士に会社設立を相談する際の費用相場は0〜5万円!そもそも必要なのか、相談しないで良いパターンも紹介
会社設立のサポートは永安栄棟税理士事務所にお任せください
永安栄棟税理士事務所では、既存のお客様や、これから顧問契約を結んでいただけるお客様 に対して、起業時の「開業支援」サービスを無料で提供しています。
具体的なサポート内容は以下のとおりです。
- 設立支援:必要な届出書の作成や司法書士・社労士の紹介など
- 資金調達支援:資金調達方法に関するアドバイス
- 設立時の運営指導:資本金、役員報酬の金額や合同会社・株式会社の選択などのアドバイス
また会社設立後の「確定申告丸投げパック」を提供しています。
サービス内容は以下のとおりです。
- 日々の会計帳簿の記帳
- 決算書の作成
- インボイスへの対応
- 消費税申告書の作成
- 確定申告書の作成
料金は以下のとおりです。
| 売上規模 | 月額報酬(毎月) | 決算報酬(年1回) |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 1万円(個人) 2万円(法人) | 12万円(個人) 12万円(法人) |
| 〜2,000万円 | 2万円(個人) 2.5万円(法人) | 12万円(個人) 16万円(法人) |
| 〜3,000万円 | 3万円 | 16万円 |
| 〜4,000万円 | 4万円 | 18万円 |
| 5,000万円超 | ご相談 | ご相談 |
弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。ぜひ以下より、各プランについて詳しく見てみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる
まとめ
会社の設立に必要な資本金の決め方や1円での設立をおすすめしない理由、資本金の平均額などについて解説しました。
理想的な資本金の額は、企業によって異なります。また、資本金のみならず役員報酬や、株式会社と合同会社どちらにするかなど、決めるべきことは複数あります。
「やっぱりこうしておけば良かった」といった後悔を避けたいのであれば、ぜひ税理士への相談をご検討ください。
弊所のサービスについては、以下よりチェックしてみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる