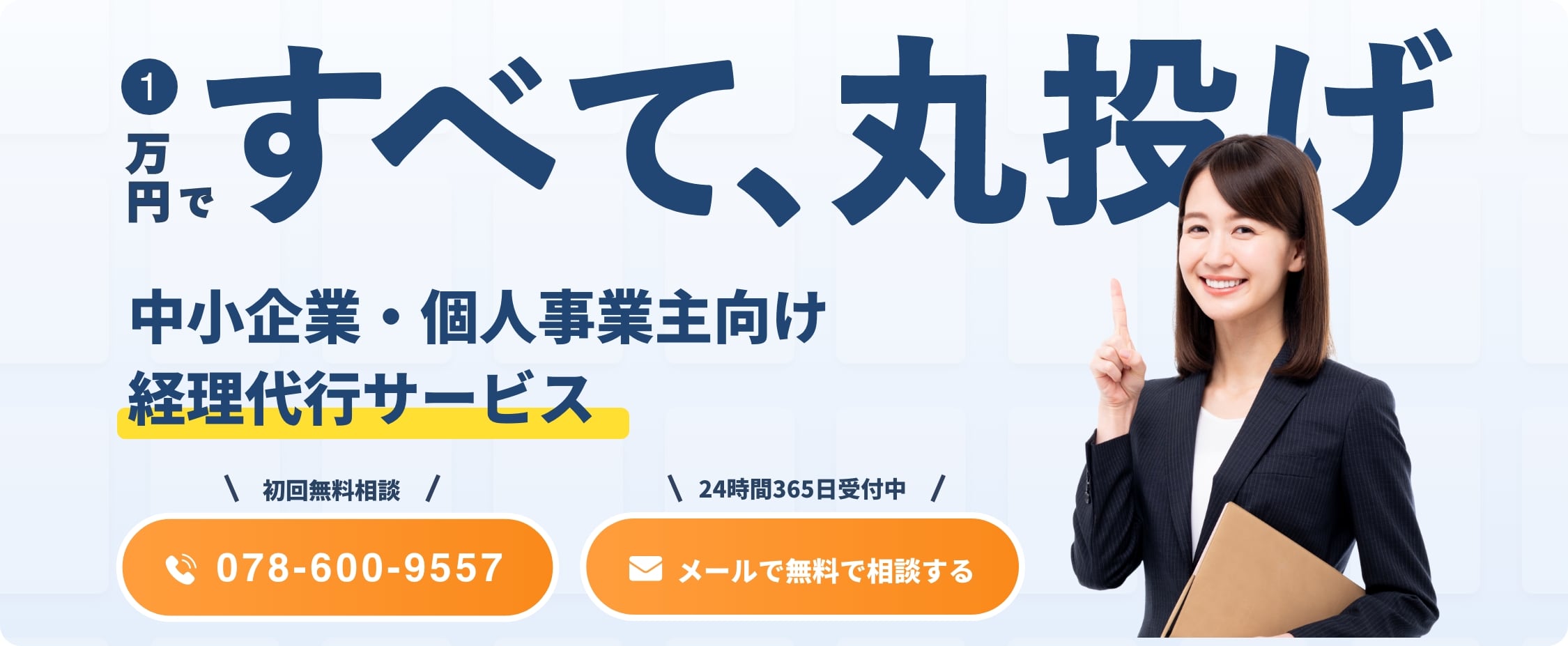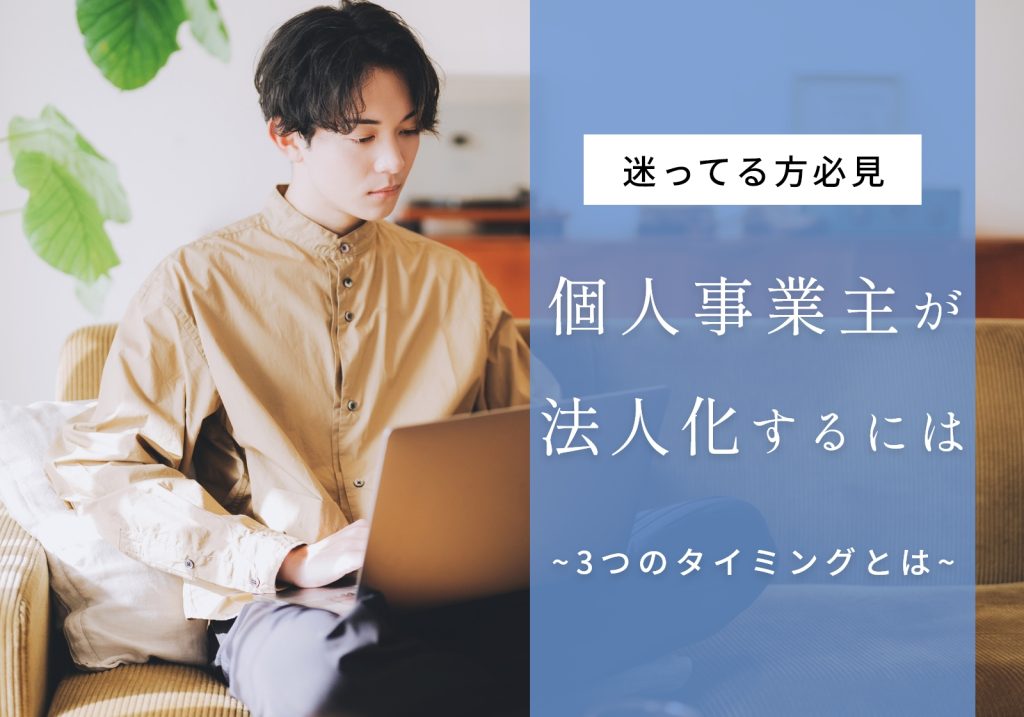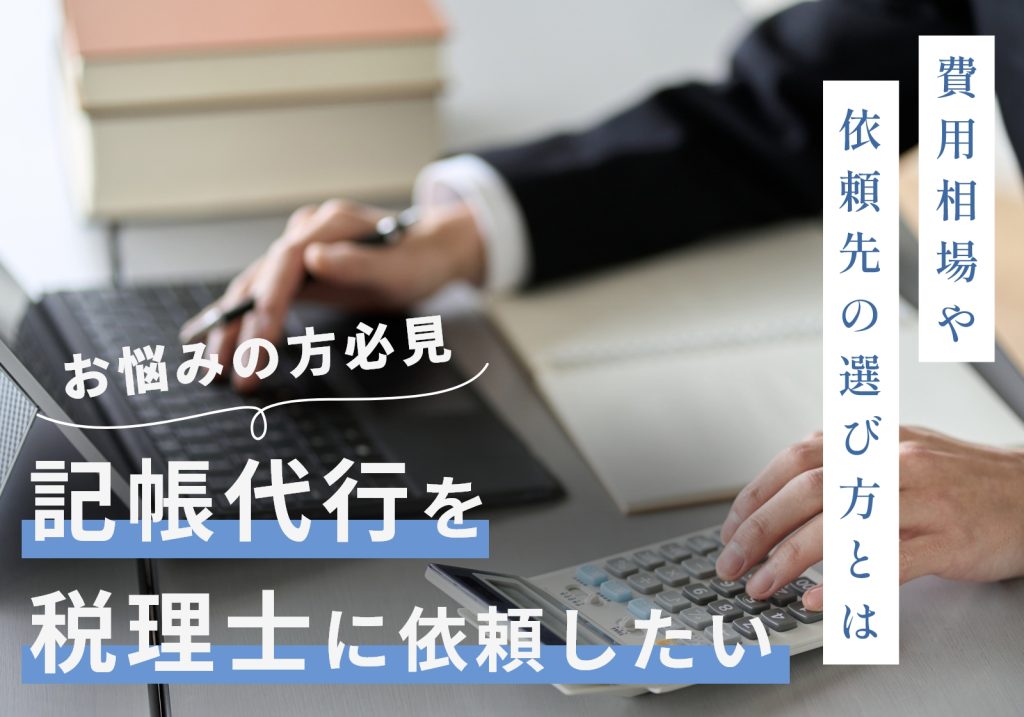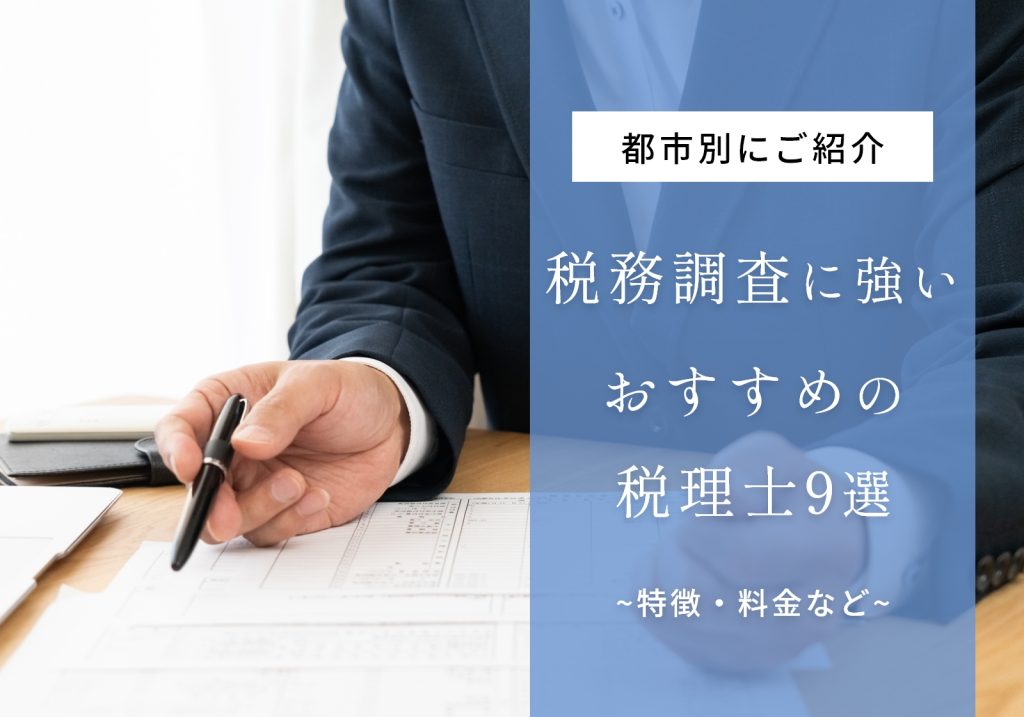税務調査後は、原則1ヶ月以内の修正申告が必要です。修正申告をしないと更正となり、追徴課税額が増える可能性があります。
今回は、税務調査で修正申告となった場合に課されるペナルティや修正申告の流れ、追徴課税額を少しでも減らす方法などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、修正申告に関する不安がなくなります。
目次
税務調査における修正申告とは?
確定申告で申告漏れや計算ミスが疑われると、税務調査の対象になります。
税務調査の結果、本来納めるべき税額よりも少なく申告していたことが判明した場合、修正申告が必要です。
例えば、本来100万円納税すべきところを70万円しか納めておらず、再度申告をして差分の30万円を納税するといった形です。
税務署は、限られた労力を使って、税務調査を実施しています。申告漏れや計算ミスの可能性が高い人物でなければ、そもそも税務調査の対象にはなりません。
そのため税務調査では、80%近い確率で申告漏れや計算ミスを指摘されるとも言われています。
税務調査の対象になったのであれば、多かれ少なかれ修正申告が発生すると覚悟しておきましょう。
税務調査で修正申告となった場合に課される主なペナルティ
税務調査で修正申告となった場合、必要に応じて以下のペナルティが課されます。
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
例えば100万円納税すべきところを70万円しか納めていなかった場合、差分の30万円だけでなく、場合によっては+αの税金を支払わなければなりません。
上記4つの税金について、それぞれ詳しく解説します。
延滞税
延滞税は、本来の納付期限までに税金が納付されなかった場合に、遅延した日数に応じて課される税金です。
日数が長期になるほど、税額は高くなります。また、延滞期間が2ヶ月を超えるか否かで、税率は大きく変わります。
延滞税の計算式は、以下のとおりです。
未納額×利率×日数÷365
利率は年度によっても変わります。
2025年の場合、納付期限の翌日から2ヶ月以内だと利率2.4%、2ヶ月を過ぎた日数については利率8.7%です。
例えば3ヶ月遅れて納付した場合、最初の2ヶ月には2.4%、最後の1ヶ月には8.7%の利率が適用されます。
そのため、延滞税の額を少しでも抑えたいのであれば、早めの修正申告が欠かせません。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告した税額が実際に支払うべき額よりも少なかった場合に課される税金です。
税務調査で経費が否認されたり、売上の計上漏れが発覚したりすると、過少申告加算税の対象となります。
また、支払った税額が本来支払うべき額よりも少なければ少ないほど、過少申告加算税は大きくなります。
過少申告加算税の計算式は、以下のとおりです。
増差額×10%
しかし、「期限内申告税額と50万円のどちらか多い金額を超過する部分」については、税率が10%ではなく15%になります。
例えば当初申告した税額が300万円で、修正後の課税額が700万円のケースを例に考えてみましょう。
この場合、増差額は700万円−300万円で400万円です。
増差額400万円は、当初申告した税額300万円を100万円超過しています。
そのため増差額300万円分には10%の税率、増差額100万円分には15%の税率が適用されます。このケースにおける過少申告加算税額は、以下のとおりです。
300万円×10%=30万円
100万円×15%=15万円
→合計45万円の過少申告加算税
無申告加算税
無申告加算税は、申告を期間内に行わなかった場合に課される税金です。
税率は、以下のように納税額によって異なります。
- 納税額50万円以下:15%
- 納税額50万円超300万円以下:20%
- 納税額300万円超:30%
例えば納税額が400万円の場合、無申告加算税額は以下のとおりです。
50万円×15%=7.5万円、250万円×20%=50万円、100万円×30%=30万円
→これら3つを合計すると、無申告加算税額は87.5万円
無申告加算税の税率は、先ほど解説した過少申告加算税よりも高くなっています。税務署が、無申告を過少申告よりも重く捉えていることが分かります。
関連記事:【個人事業主向け】「無申告でも税務調査が来ない」は間違い!来る確率や今からできる対策を紹介
重加算税
重加算税とは、税額を算出する際に必要な情報を隠蔽するなどして、不正を行った場合に課される税金です。
隠蔽の例としては、証拠書類の破棄や帳簿への虚偽の記載などがあります。
重加算税は、悪質性が高いと判断される場合に、ここまで紹介した過少申告加算税や無申告加算税に代える形で課されます。
重加算税の税率は、以下のとおりです。
- 申告書を提出していた場合:35%
- 申告書を提出していなかった場合:40%
- 隠蔽を繰り返した場合:追加で10%
税務調査で修正申告となった場合は、延滞税に加えて、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税のいずれかを支払うのが一般的です。
これらの税金については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:税務調査の追徴課税とは?5つの種類や各何パーセントか、払えないとどうなるかを解説
税務調査後に修正申告をする流れ
税務調査後の修正申告は、以下の流れで行われます。
- 修正申告書を作成・提出する
- 差額と延滞税を支払う
- 必要に応じて加算税を支払う
1つずつ詳しく見てみましょう。
修正申告書を作成・提出する
税務調査で合意した内容に沿って、修正申告書を作成します。
国税庁が公開する、修正申告書の雛形は以下のとおりです。
作成した修正申告書を提出する方法は3つあります。
- 郵送
- 電子申告
- 窓口提出
おすすめは、24時間365日提出できて手間もかからない電子申告です。
差額と延滞税を支払う
修正申告書の提出と同日に、追加で納めることになった税金(本税)と、それに対する延滞税を支払います。
これら税金は、税務署窓口や金融機関のみならず、口座振替やクレジットカードでも納付可能です。
必要に応じて加算税を支払う
場合によっては、本税と延滞税のみならず、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税といった加算税の支払いも必要です。
加算税額は、税務署から届く賦課決定通知書にて確認できます。
国税庁が公開する賦課決定通知書の雛形は以下のとおりです。
なお税理士に税務調査への対応を依頼している場合、修正申告まで任せられます。
関連記事:税理士への税務調査立ち会い依頼時の費用相場は30〜70万円!メリットや流れを解説
税務調査後の修正申告における納付期限はいつまで?
税務調査後の修正申告で課される税金には、延滞税・無申告加算税のように複数の種類があります。そして支払う税金によって、納付期限は異なります。
まず、追加で納めることになった本税と延滞税は、修正申告書の提出日に納付するのが一般的です。
また、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税は、賦課決定通知書の発行日から1ヶ月以内に支払わなければなりません。
税務調査後に修正申告をしないとどうなる?
税務調査にて修正申告を促されたにもかかわらず、修正申告に応じなかった場合、税務署によって更正の手続きが行われます。
更正とは、修正申告が行われなかった場合に、税務署が納税額を決定する手続きのことです。
「わざわざ修正申告をしなくても、税務署が更正で納税額を計算してくれるのなら、そちらの方が楽では?」と考える方がいるかもしれません。
たしかにルール上は、そのとおりです。
しかし税務調査では、受け答えなどによって結果が大きく変わります。場合によっては、ある程度妥協してもらえることもあるでしょう。
一方で更正の場合は、税務署が法律に則って手続きを行います。そのため一切妥協をしてもらえず、結果として支払う税金の額が多くなる可能性があります。
税務調査における修正申告と更正の請求の違い
修正申告とよく似た言葉として「更正の請求」があります。しかし両者には、まったく逆の意味があります。
修正申告は、納めた税額が少な過ぎた場合に、自ら誤りを訂正して納める税額を増やすための手続きです。
一方で更正の請求とは、納めた税額が多過ぎた場合に、納税者が税務署に対して「払い過ぎた税金を返してください」と税額を減らしてもらうようにお願いする手続きのことです。
その請求が通ると更正が行われ、場合によっては払い過ぎた税金が戻ってきます。
税務調査前に自ら修正申告をするとペナルティを回避or軽減できる
修正申告は、いつでも行えます。税務調査の対象になっていなくても、誤りに気付いた場合は修正申告が可能です。
修正申告では、本税に加えて以下のペナルティが課されるとお伝えしました。
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
しかし税務調査で指摘される前に、自ら修正申告を行うと、これらのペナルティを回避または軽減できます。
誤りに気付いたのであれば「いつバレるか」と怯えて過ごすのではなく、できるだけ早めに修正申告を行いましょう。
「自主的な修正申告が税務調査を誘発する」は間違い
税務調査の対象になる前に、自ら修正申告を行うと「この会社は詳しく調べれば他にも誤りが見つかるかもしれない」とかえって怪しまれ、税務調査を誘発すると考える方がいます。
しかしこれは、完全な誤解です。むしろポジティブな評価を受けるでしょう。
また、上記のような考えから修正申告をしないと、いずれ税務調査の対象になって多額の追徴課税を課されます。
今正直に修正申告をすることが、数年後の数十万円、数百万円の節約につながります。
税務調査や修正申告への対応は税理士への相談がおすすめ
税理士に頼らず、自力で税務調査やその後の修正申告への対応を行うことも可能です。
しかしそれだと、税務調査でうまく質問に答えられないなどして、不利な条件を飲まされてしまいます。
また、税務調査の準備や修正申告の手続きには、膨大な時間がかかります。
そこでおすすめなのが、税理士への相談です。
税理士に依頼をすれば、税務調査の準備から当日の対応、修正申告まですべてサポートを受けられます。
たしかに費用はかかりますが、税理士の立ち会いによる追徴課税額の減少や手間の削減により、十分元を取れます。
税理士への相談について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
関連記事:税理士への税務調査立ち会い依頼時の費用相場は30〜70万円!メリットや流れを解説
税務調査や修正申告は永安税理士事務所におまかせください
永安栄棟税理士事務所では、税務調査完全サポートパックを提供しています。プランの詳細は以下の通りです。
- 事前打ち合わせ・資料確認
- 調査の立ち会い
- 税務署との調整
- 修正申告書の提出
料金は30万円〜となっており、要望に応じて最適なプランを提案させていただきます。
永安栄棟税理士事務所では、税務調査歴40年超の元特別国税調査官をはじめとしたスタッフが、豊富な経験をもとにサポートいたします。
これまでサポートを行ったほぼすべてのお客様が、税務調査サポート費用を上回る追徴課税の減少を実現しました。

弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。プラン詳細については、以下をチェックしてみてください。
まとめ
税務調査で修正申告となった場合に課されるペナルティや修正申告の流れ、追徴課税額を少しでも減らす方法などについて解説しました。
修正申告で支払う追徴課税額を少しでも減らすには、税務調査の通知が届いた段階での税理士への相談が欠かせません。
>>永安栄棟税理士事務所の「税務調査完全サポートパック」を詳しく見てみる
また、そもそも税務調査の対象にならないように、正しく確定申告を行うことが大切です。
永安栄棟税理士事務所でも「確定申告丸投げパック」を提供しています。詳しくは以下をチェックしてみてください。