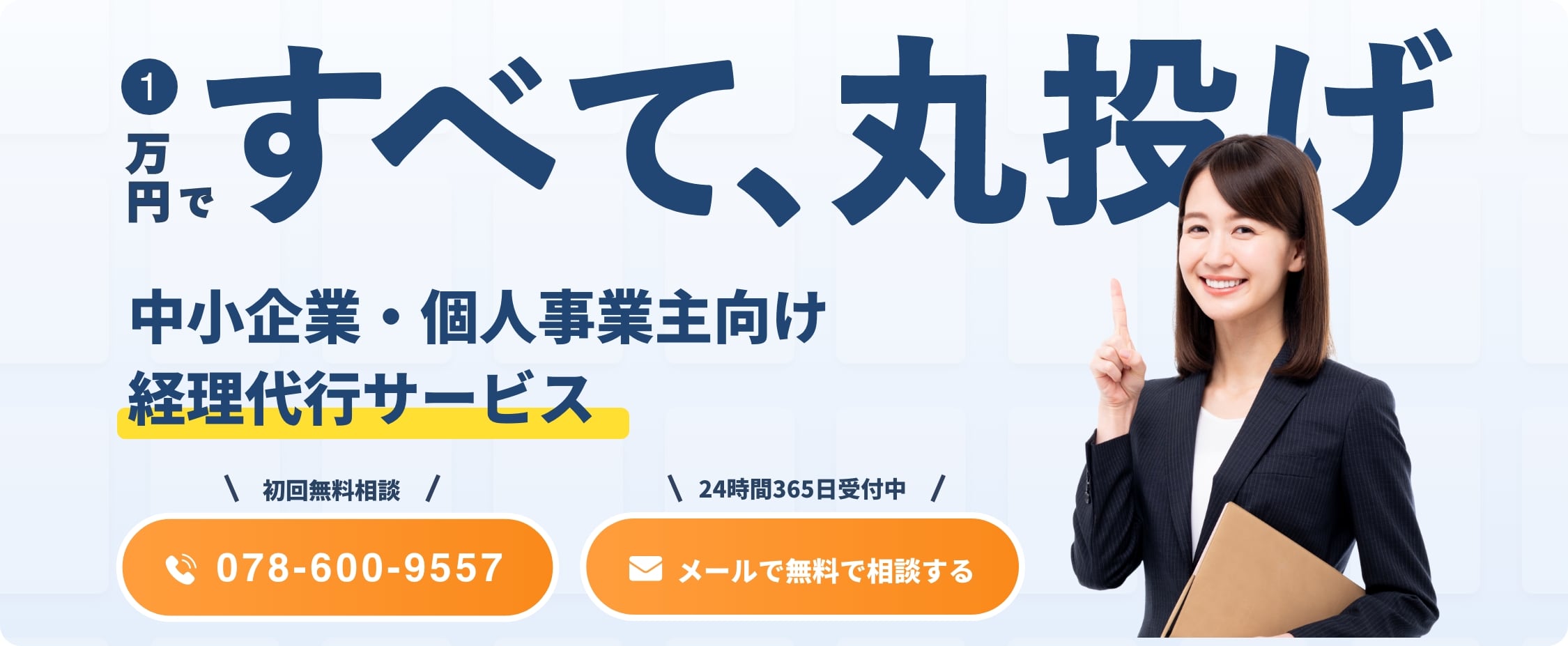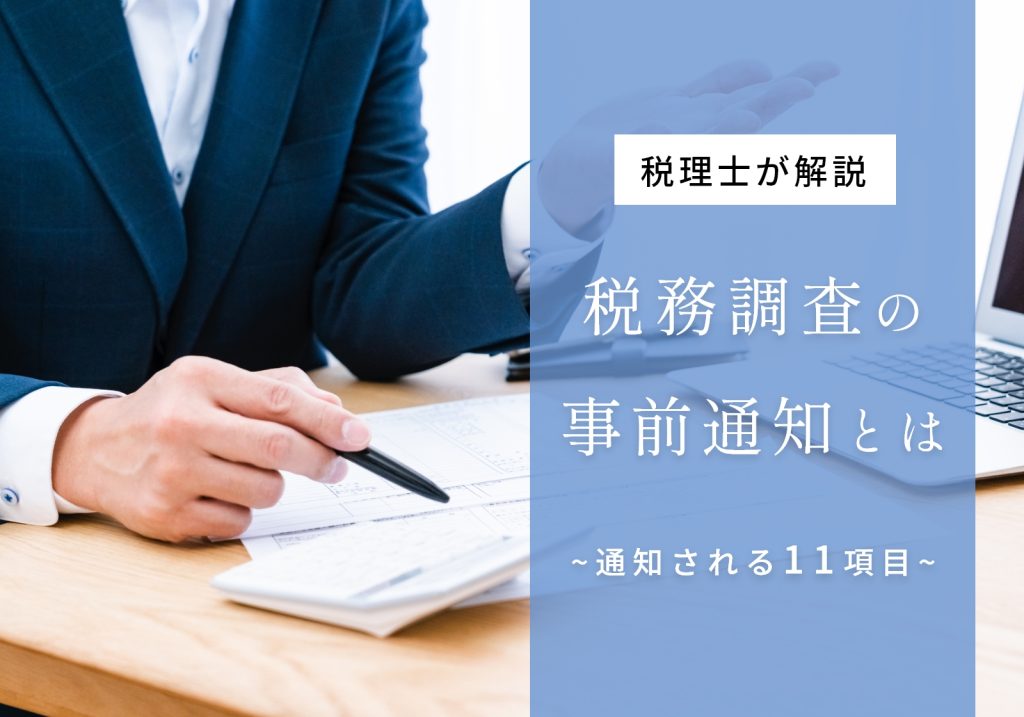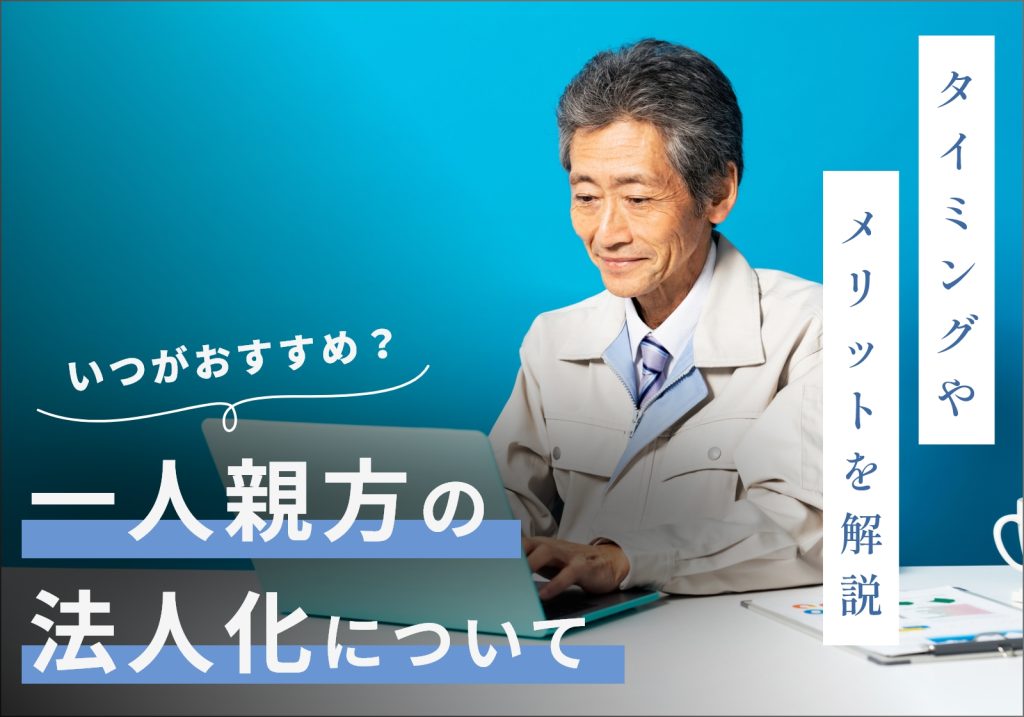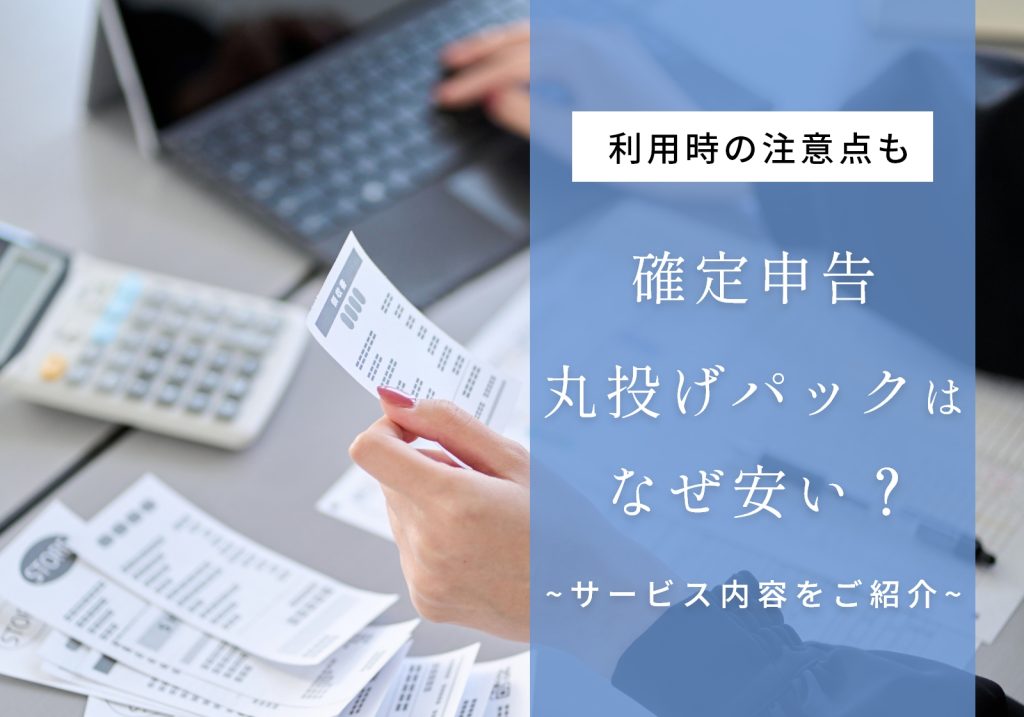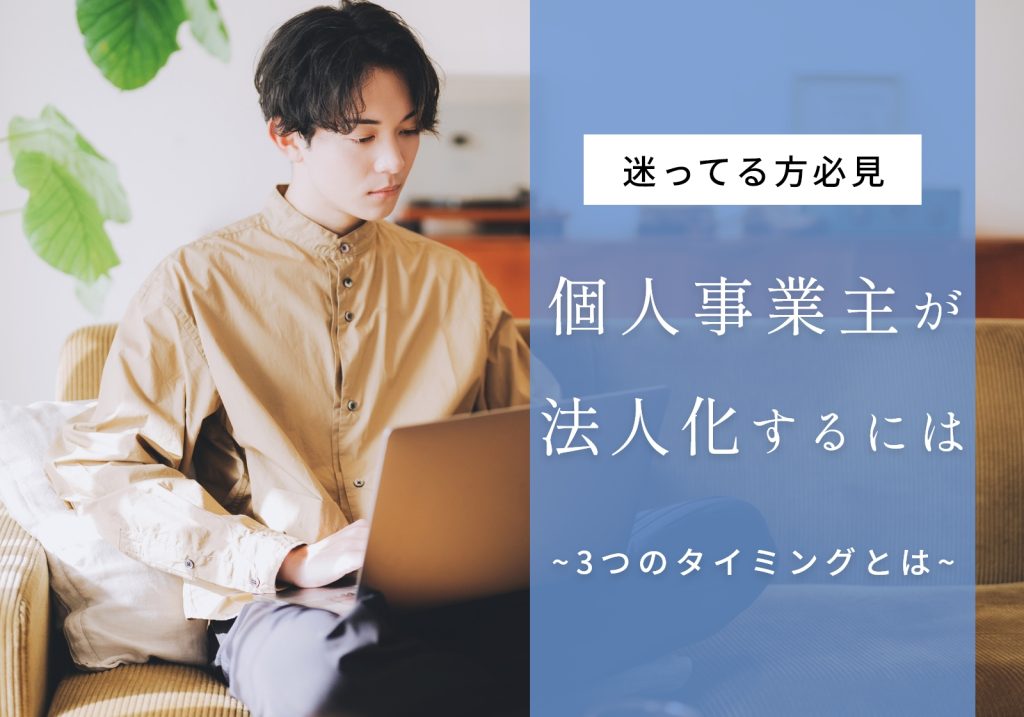
個人事業主が法人化を検討すべきタイミングは、所得が800万円を超えた時・売上が1,000万円を超えた時・資金調達や事業拡大をしたい時の3つです。
適切なタイミングで法人化をすれば、いくつものメリットが得られます。一方で、タイミングを間違えるとデメリットになります。
「個人事業主として生計を立てており、法人化すべきか否か迷っている」という方もいらっしゃるでしょう。
今回は、個人事業主が法人化を検討すべき3つのタイミングやメリット・デメリット、法人化の際に受け取れるお得な助成金などについてまとめました。
税理士の立場から、難しい用語は極力使用せず、分かりやすく解説します。
記事を最後までチェックすれば、あなたが法人化すべきか否かが明確になります。
目次
個人事業主と法人化の違いは?
個人事業主と法人化の主な違いを、以下にまとめました。
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 事業開始に必要な提出書類 | 開業届 | 定款、登記事項証明書など |
| 事業開始にかかる費用 | なし | 最低24万円 |
| 主な税金 | 所得税 | 法人税 |
| 経費の範囲 | 限定的 | 個人事業主より広い |
| 社会的信頼 | 法人に比べて低い | 高い |
| 資金調達 | 小規模が大半 | 大規模での資金調達も可能 |
| 赤字の繰越 | 3年 | 10年 |
| 責任範囲 | 無限 | 有限 |
これらの違いが、具体的にどのような影響を及ぼすのかについては、記事内で解説します。今の時点では、上記の違いについて詳細に把握しておく必要はありません。
まずは「個人事業主の方が敷居が低くて気軽だが、法人の方ができることが多い」くらいの認識で構いません。
個人事業主が法人化をするタイミング、目安は3つ
個人事業主が法人化をする主なタイミング、目安は以下の3つです。
- 所得が800万円を超えた時
- 売上が1,000万円を超えた時
- 資金調達や事業拡大をしたい時
それぞれ詳しく解説します。
所得が800万円を超えた時
所得税は、収入から必要経費や控除を引いた課税所得をもとに算出されます。
以下は、個人事業主の所得税率をまとめた表です。
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上 | 45% |
一方、法人税の税率は23.2%です。
つまり個人事業主の所得が8,999,000円を上回ると、法人税の方が税率が低くなります。
そのため、課税所得が800万円を超えたあたりが、個人事業主が法人化を検討する1つのタイミングとされています。
売上が1,000万円を超えた時
2年前の売上高が1,000万円を超えた個人事業主は、その年から消費税を納めなければなりません。
※インボイス制度に登録している場合は、売上規模にかかわらず納税義務が発生します。
しかし、そのタイミングで法人化をすれば、消費税の納税を最大で2年間後ろ倒しにできます。
なぜなら新しく設立された法人は、原則として2年間消費税の支払いが免除されるからです。
個人事業主は、2年前の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じるとお伝えしました。このルールは法人も同じです。
法人設立1年目と2年目には、「2年前の売上」が存在しません。そのため消費税の納税が免除されるという仕組みです。
以上から、売上が1,000万円を超えたタイミングが、法人化を検討する1つの目安とされています。
資金調達や事業拡大をしたい時
個人事業主と法人では、信用力に大きな違いがあります。
個人事業主の場合、大規模な融資を受けるのは難しいでしょう。また、「法人格を持つ相手でなければ取引をしない」と定めている企業も少なくありません。
個人事業主であることが、ビジネスチャンスを逃す原因になり得ます。
法人化をすれば、個人事業主とは比較にならない、社会的信用を獲得できます。金融機関からは、より大きな資金調達ができるようになるでしょう。
また、株式会社という看板が、企業との契約や人材の採用などあらゆる場面でプラスに働きます。
法人化をすれば、事業の成長スピードを一気に加速させられます。そのため、資金調達や事業拡大をしたい時が、法人化を検討すべき1つのタイミングです。
個人事業主が法人化をするメリット
個人事業主が法人化をするメリットは、以下の3つです。
- 節税ができる
- 決算月を自由に設定できる
- 赤字を長期間繰り越せる
1つずつ詳しく見てみましょう。
節税ができる
個人事業主が法人化をする最大のメリットは、節税です。
記事前半で解説した、所得税率と法人税率の差や消費税の猶予のみならず、経費の範囲拡大による節税効果も期待できます。
個人事業主が法人化をすることで、経費計上できるようになる費用の例は以下のとおりです。
- 福利厚生費
- 車両関連費
- 出張旅費
- 家賃・社宅
- 退職金
法人化によって経費計上できる範囲の拡大については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:個人事業主は法人化することで経費計上できる範囲が拡大する
決算月を自由に設定できる
個人事業主の会計期間は、法律で1月1日から12月31日までと決まっています。会計期間の変更はできません。
そのため確定申告は、毎年2〜3月にかけて行う必要があります。
なかには、確定申告の期間が事業の繁忙期と重なり、困っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし法人の場合は、会計期間を自由に設定できます。つまり、1年のうち好きな月を、決算月として選ぶことができるのです。
繁忙期を避けて、比較的落ち着いている月を決算月に設定すれば、余裕を持って決算作業や納税準備を進められるでしょう。
また、大きな設備投資や広告宣伝費などの支出が予想される月の直後を決算月とすれば、期末の節税対策を計画的に実行しやすくなります。
赤字を長期間繰り越せる
事業を運営していると、さまざまな要因で赤字が発生する可能性があります。
この赤字を翌年以降の黒字と相殺して、税金の負担を軽減できる制度が「繰越欠損金の控除」です。
そして、赤字を繰り越せる期間は、個人事業主か法人かで異なります。
まず、個人事業主が赤字を繰り越せる期間は、最大3年間です。続いて法人が赤字を繰り越せる期間は、最大10年間です。
この7年間の差は、長期的な視点が求められる事業において、経営の安定性に大きく貢献します。
大きな赤字が出た場合、3年間では相殺しきれないかもしれません。一方10年間の場合は、赤字を相殺しきれる可能性が高まります。
赤字が出る可能性が高い事業形態の場合には、大きなメリットとなるでしょう。
個人事業主が法人化をするデメリット
個人事業主が法人化をするデメリットは、以下の3つです。
- 費用がかかる
- 社会保険に加入する必要がある
- 自力での確定申告が難しくなる
それぞれ詳しく見てみましょう。
費用がかかる
個人事業主が法人化をして、株式会社を設立する場合、最低でも24万円の費用がかかります。
費用の内訳は以下のとおりです。
- 定款費用
- 登記費用
- 資本金
さらに、法人化の手続きを司法書士などに依頼する場合、追加で費用がかかります。
また、たとえ事業が赤字であっても、法人住民税の均等割として毎年最低7万円程度を支払わなければなりません。
法人化をすると、税務申告が複雑になります。そのため、税理士への顧問料も必要となります。
これらの費用よりも、法人化によるメリットの方が大きいかどうかが、決断する1つの基準です。
法人化によってかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:個人事業主から法人化する際の費用は最低24万円!後悔しないタイミングや年間費用についても紹介
社会保険に加入する必要がある
個人事業主の多くが、国民健康保険と国民年金に加入しています。しかし法人化をすると、健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
そして前者よりも後者の方が、保険料負担は大きくなります。
社会保険料(健康保険や厚生年金)は、会社と従業員による労使折半が原則です。会社員の給与明細から天引きされるのは自己負担分で、会社はそれと同額を別途納付しています。
そして個人事業主が法人化をして一人社長となる場合、会社分と従業員(あなた)分の両方を、負担しなければなりません。
従業員を雇用すれば、その従業員の社会保険料の半額は、会社の負担となります。
事業の利益が安定していない状態で法人化に踏み切ると、この社会保険料の支払いが、キャッシュフローを圧迫するリスクとなります。
自力での確定申告が難しくなる
個人事業主の確定申告は、会計ソフトなどを使えば、自力で行うことも不可能ではありません。
しかし法人の税務申告は、個人事業主よりも複雑です。そのため、税理士への依頼が原則です。
個人事業主の中には、費用を節約するため、税理士へ依頼をせずに自力で確定申告を済ませていた方もいらっしゃるでしょう。
そういった方は、税理士事務所を探す手間と、毎月2万円からの費用がかかる点を考慮しなければなりません。
個人事業主と法人はどっちが得?
「結局、個人事業主と法人はどちらが得なの?」という問いに対する答えは「その事業者の状況次第」としか言えません。
事業のステージや規模、将来の展望などによって、最適な形は変わってきます。
例えば、事業を始めたばかりで売上や所得が少ない段階では、設立や運営にコストがかからず、手続きも簡単な個人事業主の方が有利でしょう。
一方で、事業が成長して所得が800万円を超え、さらなる事業拡大や社会的信用力の向上を目指す段階になれば、法人化をした方が得になるでしょう。
重要なのは、現在の自分の事業がどのステージにあり、今後どこを目指しているのかを明確にすることです。
税金・コスト・信用力・手間など、複数の観点から考える必要があります。
個人事業主が法人化する際に受け取れる融資制度
個人事業主が法人化をする際は、以下のような融資制度を活用できます。
- 日本政策金融公庫の融資制度
- 地方自治体の融資制度
日本政策金融公庫が実施する「新規開業・スタートアップ支援資金」を活用すれば、最大で7,200万円の融資を受けられます。
利用対象は、新たに事業を始める方か、事業開始後おおむね7年以内の方です。返済期間は20年以内となっています。
また、地方自治体は、それぞれ独自の融資制度を提供しています。自身が居住している地方自治体の融資制度について、調べてみるのも良いでしょう。
個人事業主が法人化する際に利用できる創業融資については、以下の記事で解説しています。
関連記事:法人成りで利用できる創業融資を解説!審査通過率を高める方法も
個人事業主の後悔しない法人化は税理士への相談がおすすめ
以下2つの理由から、個人事業主の後悔しない法人化は、税理士への相談がおすすめです。
- 損しない最適な選択肢を選べるから
- 法人化後の依頼はほぼ必須だから
1つずつ詳しく解説します。
損しない最適な選択肢を選べるから
「課税所得800万円」や「売上1,000万円」といった法人化の目安は、あくまで一般論に過ぎません。
法人化をして後悔しないためには、一般論を自身の状況に当てはめて、本当にメリットがあるのかを考え直す必要があります。
例えば、売上が1,000万円を超えていても、法人化をしない方が良いケースもあるでしょう。
そして、法人化すべきか否かを的確に判断したいのであれば、税理士への相談がおすすめです。
「今すぐ法人化すれば年間〇〇円程度のメリットがある」「売上がこのくらいになるまでは個人事業主を続けた方が得になる」といった判断が可能となります。
関連記事:起業したら税理士は必要?不要?費用や相談時に聞くことを解説
法人化後の依頼はほぼ必須だから
個人事業主の確定申告は、自力で行うことも可能です。しかし法人の税務申告を、自力で行うのは非現実的です。
つまり、法人化をするのであれば、税理士との顧問契約はほとんど必須と言って良いでしょう。
そして税理士事務所の中には、税務申告のみならず、法人化のサポートを行なっているところも存在します。
法人化後に顧問契約を結ぶのであれば、法人化の前からサポートを受けた方が、手間が省けますし後悔する可能性も減らせます。
個人事業主の法人化は永安税理士事務所にご相談ください
永安栄棟税理士事務所では、弊所のお客様向けに、起業時の「開業支援」サービスを無料で提供しています。具体的なサポート内容は以下のとおりです。
- 設立支援:必要な届出書の作成や司法書士・社労士の紹介など
- 資金調達支援:資金調達方法に関するアドバイス
- 設立時の運営指導:役員報酬の金額や合同会社・株式会社の選択などのアドバイス
また個人事業主や中小企業向けの「確定申告丸投げパック」を提供しています。
サービス内容は以下のとおりです。
- 日々の会計帳簿の記帳
- 決算書の作成
- インボイスへの対応
- 消費税申告書の作成
- 確定申告書の作成
料金は以下のとおりです。
| 売上規模 | 月額報酬(毎月) | 決算報酬(年1回) |
|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 1万円(個人) 2万円(法人) | 8万円(個人) 12万円(法人) |
| 〜2,000万円 | 2万円(個人) 2.5万円(法人) | 10万円(個人) 12万円(法人) |
| 〜3,000万円 | 3万円 | 14万円 |
| 〜4,000万円 | 4万円 | 16万円 |
| 5,000万円超 | ご相談 | ご相談 |
弊所は兵庫県にある税理士事務所ですが、日本全国どこからでもご依頼いただけます。ぜひ以下より、各プランについて詳しく見てみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる
まとめ
個人事業主が法人化を検討すべき3つのタイミングやメリット・デメリット、法人化の際に受け取れるお得な助成金などについて解説しました。
個人事業主が法人化を検討すべきタイミングは、所得が800万円を超えた時・売上が1,000万円を超えた時・資金調達や事業拡大をしたい時の3つです。
しかし、上記はあくまで目安です。自身の状況に当てはめて、法人化するか否かを考えなければなりません。
法人化すべきか悩む場合、法人化の手続き、法人化後の確定申告などについては、税理士のサポートがおすすめです。
弊所のサービスについては、以下よりチェックしてみてください。
>>永安栄棟税理士事務所の「開業支援」を詳しく見てみる
>>永安栄棟税理士事務所の「確定申告丸投げパック」を詳しく見てみる