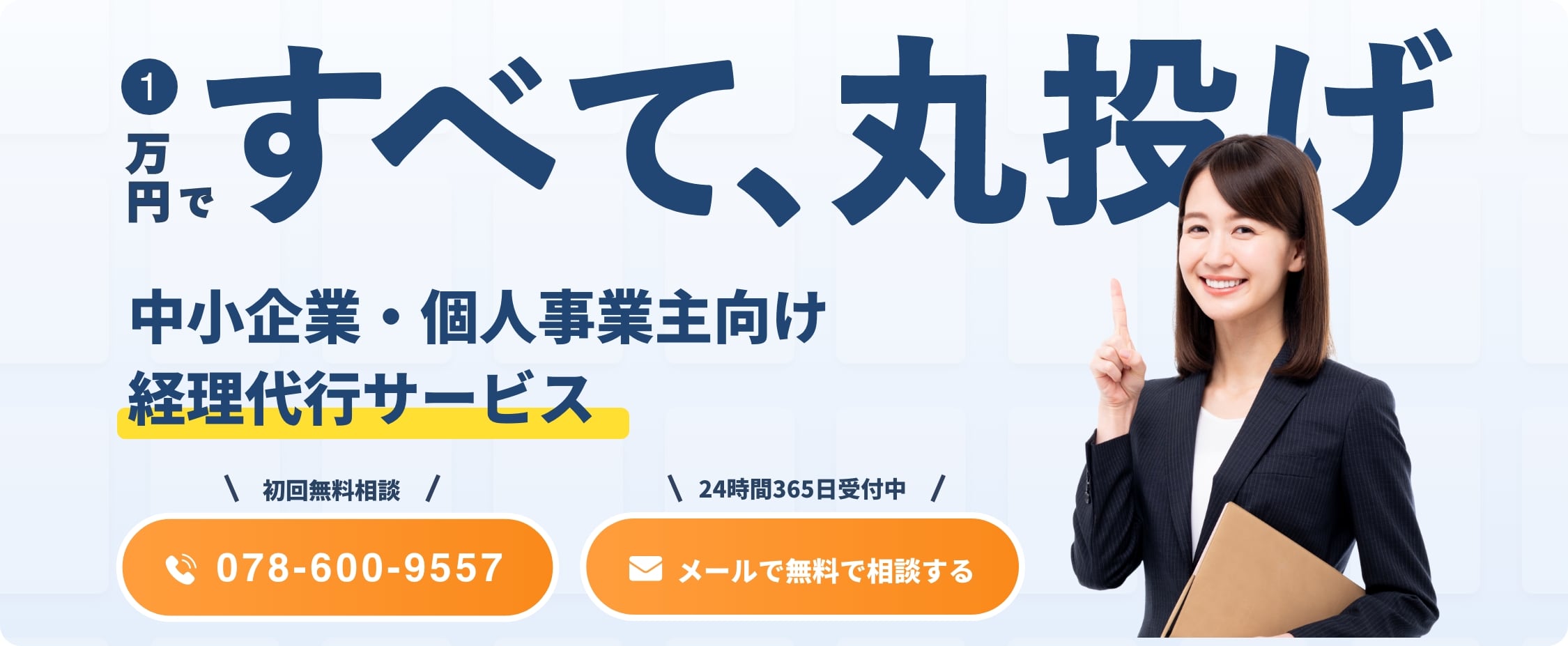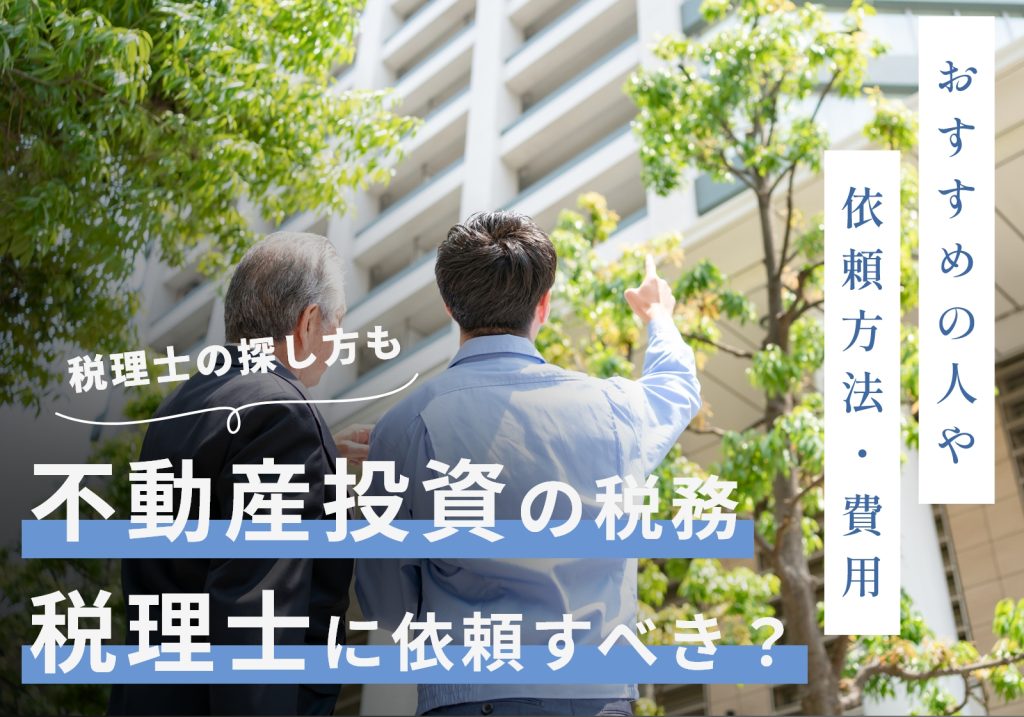役員貸付金が税務調査で狙われる理由と回避するポイントを解説
会社が経営者などに金銭を貸し付ける行為は、税務調査において厳しくチェックされます。
貸付方法や返済管理を怠ると、役員報酬とみなされて追徴課税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
本記事では、役員貸付金に関する税務上のリスクと、追徴課税を回避するための具体策について解説します。
役員貸付金とは何か
役員貸付金とは、会社が役員(代表取締役や取締役など)に対して資金を貸し付けた際に、貸借対照表で「役員貸付金」として計上される勘定科目です。
役員が借りた金銭を計画的に返済している場合、税務上の問題になることはありません。
しかし、返済の実態がないケースや、私的流用とみなされるときは、税務リスクが生じます。
また、税務調査において役員貸付金が否認された場合、役員報酬の隠蔽や源泉徴収漏れと判断される可能性があるため、契約書の作成や返済管理を適切に行うことが不可欠です。
役員貸付金が税務調査で問題視される理由
役員貸付金は、会社資金の私的流用とみなされやすく、税務調査では重点的に確認される項目です。
実態が貸付ではなく給与や賞与と認定されると、多額の税負担が生じる可能性があります。
税務署が注目する「個人流用」の疑い
会社資金を私的に使用したと判断された場合、役員貸付金ではなく「使途不明金」や「役員賞与」として認定される懸念があります。
同族会社や、個人事業主から法人に移行した会社では、資金管理が曖昧になりやすく、税務署によるチェックが厳しくなりがちです。
返済実績がない、契約書が存在しない、利息の設定がないなど、第三者への貸付では通常考えられない状況が見られる場合、税務署は「個人流用」と疑う根拠とするため、注意が必要です。
役員賞与・役員報酬と認定されるリスク
役員貸付金に利息が設定されておらず、返済も滞っている場合、税務署はその金銭の供与を「役員賞与」または「役員報酬」と認定する可能性があります。
役員賞与は原則として損金不算入となるため、認定された金額は法人税の課税対象となるほか、役員個人にも所得税・住民税が課されます。
また、使途が私的消費であるとの認定を受けた場合、税務署は経済的利益の供与とみなし、過去に遡って課税処分を行うこともあります。
【税務調査が不安な方におすすめの『税務調査セットプラン』】

永安栄棟税理士事務所では、税務調査セットプランを提供しています。
税務調査歴40年超の元特別国税調査官をはじめとするスタッフが、豊富な経験をもとにサポートいたします。
<税務調査セットプランの内訳>
- 事前打ち合わせ・資料確認
- 調査の立ち会い
- 税務署との調整
- 修正申告書の提出
これまでサポートを行ったほぼすべてのお客様で、税務調査サポート費用を上回る追徴課税の減少を実現しています。
税務調査セットプランの具体的な内容については、下記のページをご確認ください。
役員貸付金の税務上のリスクとその影響
役員貸付金の処理が不適切な場合、税務上の重大なペナルティが課される可能性があります。
無利息・低利貸付に対する経済的利益課税
会社が役員に対して無利息または著しく低利で貸付を行った場合、利息相当額(令和6年中の貸付については年0.9%)と実際に支払われた利息との差額が、給与として課税されることになります。
また、法人側では利息収入の計上漏れとなるため、法人税の修正申告も必要です。
利率の設定が不適正な場合、税務署から指摘を受けることが多いため、役員貸付を行う際は、適正な利率の設定が重要です。
損金不算入となるケースと法人税への影響
役員貸付金が税務署により「役員賞与」と認定された場合、その金額は法人税法上、損金不算入となります。
つまり、会社の経費として認められず、課税所得が増加するため、法人税額が増える結果となります。
損金不算入の処理は、過年度に遡って修正申告が求められることもあり、企業の財務負担に直結します。
源泉徴収漏れによる加算税・追徴課税の可能性
役員貸付金が役員賞与と認定された場合、会社は本来徴収すべきだった源泉所得税を納付していなかったことになります。
この場合、源泉徴収漏れに対する「不納付加算税」が課されるだけでなく、納税遅延に対する「延滞税」も発生します。
さらに、税金逃れを目的とした貸付金の計上と判断された場合には、「重加算税」の対象となる可能性もあり、貸付金が否認された際の影響は極めて大きくなります。
給与課税されない無利息・低利息の貸付
役員または使用人に対して、無利息または低利で金銭を貸し付けた場合でも、次のいずれかに該当する場合には、所定利率との差額が給与として課税されることはありません。
<給与課税の対象外となるケース>
(1) 災害や病気などにより、臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に対して、その資金に充てる目的で、合理的と認められる金額および返済期間で貸し付ける場合
(2) 会社の借入金の平均調達金利など、合理的と認められる利率を設定し、その利率に基づいて貸し付ける場合
(3) 上記(1)および(2)以外の貸付であっても、所定利率により計算した利息額と実際に支払われた利息額との差額が、年間で5,000円以下である場合
これは、国税庁が定める例外規定に基づくものであり、実務上の重要な判断基準となります。
これらの条件を満たすことで、貸付によって生じる経済的利益が給与課税の対象とされることを回避できます。
なお、所定利率については、国税庁が毎年定める「特例基準割合」などが参考となります。
<参考:役員貸付金に対する利息相当額(特例基準割合)>
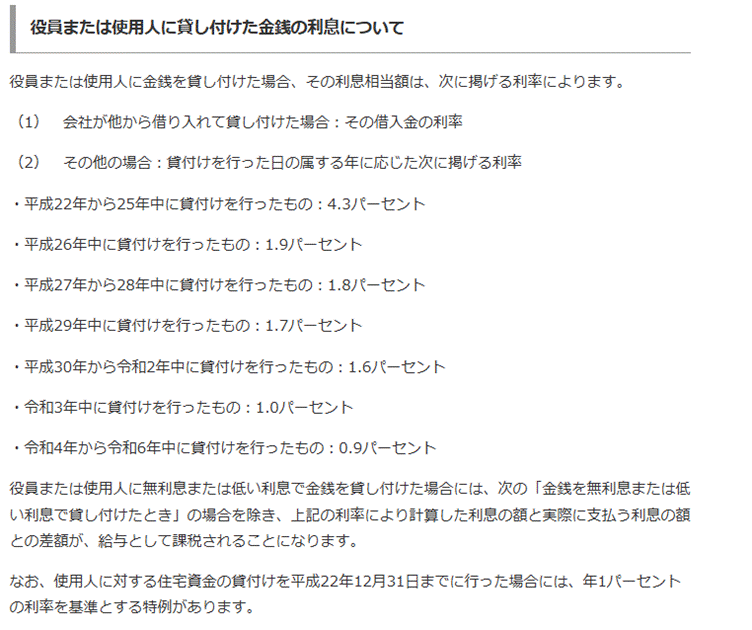
出所:No.2606 金銭を貸し付けたとき(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
税務上で役員貸付金を問題視されないための対策
役員貸付金が税務上の問題とならないためには、形式的な処理だけでなく、実態に即した管理と書面の整備が不可欠です。
金銭消費貸借契約書の作成と返済計画の明示
会社が役員に対して金銭を貸し付ける行為自体は違法ではありませんが、貸し付ける際には必ず金銭消費貸借契約書を作成する必要があります。
契約書がない場合、税務署は実質的に給与や賞与とみなされる可能性が高く、課税リスクが生じます。
契約書には、貸付金額・利率・返済期限・返済方法などを明記しなければなりません。
返済計画を具体的に定め、実際の返済履歴を帳簿に記録することで、貸付の実態を証明することができます。
なお、契約書を作成していても返済が実行されていなければ、役員貸付金は否認される可能性があるため、契約書と返済実績の両方が揃って初めて、税務上の信頼性が確保されます。
適正利率の設定と利息の収入計上
会社は営利法人であるため、役員への貸付に対しても適正な利率を設定し、利息収入を計上する必要があります。
利率の目安としては、会社が金融機関から借り入れている場合はその借入利率、そうでない場合は国税庁が定める「特例基準割合」(令和5年・6年は年0.9%)が参考になります。
無利息または低利で貸し付けた場合、差額が「経済的利益」として役員個人に課税される可能性があるため、利息の徴収と収入計上は必須です。
また、未収利息についても帳簿上で適切に処理し、税務調査に備える必要があります。
社内貸付規程の整備と運用の透明化
役員貸付金の管理を制度的に行うためには、社内規程の整備が有効です。
貸付対象者、上限額、利率、返済期間、承認手続きなどを明文化し、社内で統一的に運用することで、恣意的な貸付や税務上の疑念を回避できます。
特に中小企業では、経営者の裁量で資金移動が行われがちですが、社内ルールに基づいた運用を徹底することで、税務署からの信頼を得やすくなります。
また、定期的な残高確認と返済状況のレビューも、透明性確保のために欠かせません。
【税務手続きに不安がある方は『丸投げパック』をご利用ください!】
日々の経理業務や税務申告を効率化したいとお考えの方に向けて、当事務所の提供するサポート体制をご紹介します。